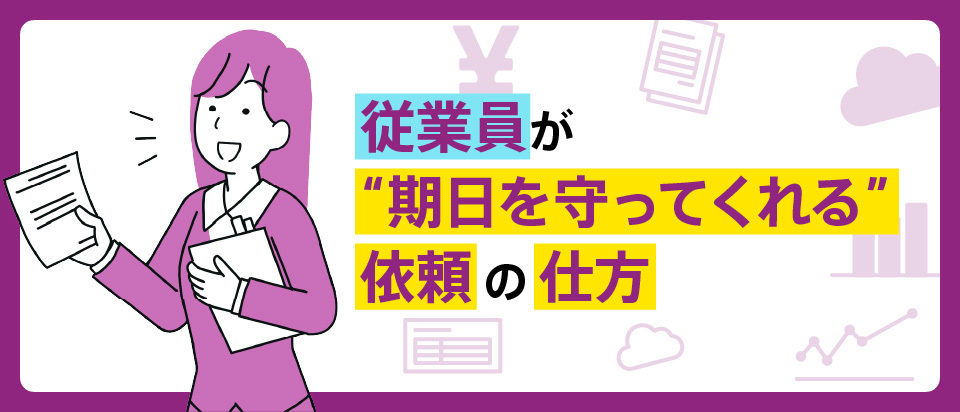会社の経営状況を把握し、必要に応じて計画を軌道修正するために必須な「予実管理」。あなたの会社ではどれくらいの頻度でどのように行われていますか?そしてあなたの会社の管理方法は適切だと感じますか?今回は、4名体制で経理業務を担っている会社から代表し、予実管理の方法についてOさんにお話を伺いました。
自社の管理方法との違いなどを確認し、業務改善にお役立てください。
スプレッドシートを使い各事業部から金額を収集、システムを活用して予実管理を実施
――まずは御社と御社の経理体制について、簡単にご紹介いただけますか?
Oさん:弊社は社員数100名以上の上場企業です。経営管理本部長のもと、経理担当は4名で担当しています。
――ありがとうございます。今回は御社の「予実管理」についてお話を伺っていきたいと思います。まずは、そもそも予算額をどう管理しているのかについて教えていただけますか?
Oさん:予算の計画については、上司である経営管理本部長が取りまとめをしています。予算作成時は各事業部からスプレッドシートに予算金額を記入していただき、それを取りまとめるという形を採っています。承認された予算は予実管理用のシステムに登録されます。
毎月の予算実績の比較については、月次の処理完了後に会計管理システム から仕訳帳を書き出し、予算実績管理用システムに実績データをアップし分析する感じですね。
――予実管理用のシステムへの対応も本部長がご対応されていらっしゃるんですか?
Oさん:いえ、そこは私が担っています。予実管理用のシステムから、さらにデータを書き出して、最終的にはExcelで取締役会に提出する資料を作成しています。差異要因はシステムを見ながらExcelに書き込みますが、まだまだ分析が甘く、経営管理本部長にフォローしていただいてます。
――システム活用することでスムーズに管理できていますか?
Oさん:はい。以前はそれらをすべてExcelでやっていたのですが、かなり膨大な量になってしまい、「開かない」「動かない」ということがあり、システムを導入しました。細かなところまで確認、分析ができるシステムなので便利です。
――それは便利そうですね。会計管理システムからデータを入れているということは、予実管理も基本的に会計データがベースになっているということで合っていますか?
Oさん:おっしゃる通りです。
――話は戻りますが、現場の方々が最初にスプレッドシートで収集していくということですが、実際に勘定科目単位で管理するという考え方を現場の方々も理解されていらっしゃるということでしょうか。
Oさん:まだちょっと怪しい感じはしますが、事業部でもきちんと理解して、管理はできていると思います。
――なるほど。お話を聞いていて、システムを活用しながら、うまく事業部を巻き込み予実管理されているのかなと感じました。経理の皆さんで管理されているシステムは事業部の方も閲覧可能なんですか?
Oさん:はい、予実管理用のシステムは、権限の設定がされていますが、各事業部の方も自分たちの事業部の内容は見られるようになっています。
――なるほど。会計の実績ベースで予算組をされていて、現場の方も同じシステムで確認できると考えると、乖離の少ない正しい予実管理ができていらっしゃるのかなと感じました。
たとえば、懇親会が立て込むなどして経費をちょっと使いすぎてしまったときなどに、現場のマネージャーが把握することができ、経理と連携が取れる体制が整っている印象です。
Oさん:そうですね。これば「経費」で申請したと思いますが「原価」ですか?と質問をいただくこともありますし、展示会の予定がずれた場合などはこちらから質問すると「あ、これは月ずれですね」といった話が出ることはあります。実態の把握がしやすいことは管理のしやすさに繋がっていると思います。
業務のチェックリストなどを活用し、属人化させない経理体制づくりを
――話は変わりますが、続いて予実管理の頻度についても伺っていきたいと思います。
Oさん:毎月予算実績の比較資料を作成して、取締役会に提出しています。
――粒度についてはいかがですか?
Oさん:BS科目については予実というより、期首の数字と現在との増減額について分析を行っています。PL科目については、弊社に3つあるセグメントと管理部門に分け、各セグメントごと、金額の大きな科目について分析をしています。
――「金額の大きな科目」とは、具体的にどういうものですか?
Oさん:売上高や人件費や広告宣伝費などですね。
――なるほど。このような金額の大きな科目も、まずは事業部で管理していくということですね。
Oさん:売上関係については事業部でKPIなどの分析を行っていますが、原価や経費関係の分析は経理グループで行ってます。
――予算額関係なく同じルーティンで管理されているんですね。ちなみに、予算計画の策定はどのようなスケジュール感で進めていかれるのでしょうか。
Oさん:決算期末が10月末なので、7月くらいに事業部に1次予算を作成してもらい、その後、社長、事業本部長、経営管理本部長で、摺合せと修正を繰り返しながら最終予算作成し、10月の取締役会で承認するというスケジュールで進めています。
――項目はいくつぐらいあるんですか?
Oさん:事業によって異なりますが、各セグメントで原価科目と経費科目で各10科目ぐらいです。
――分析時に見ていらっしゃるのは、前月対比や前年対比になりますか?
Oさん:そうですね、基本的には予算と実績の対比になります。四半期ごとの決算時には開示がありますので、前期比較や四半期推移も合わせて分析しています。
――策定した予算に対して、実績の推移を見ていかれるなかで、修正をしていくタイミング、見直しを入れるタイミングはありますか?
Oさん:前期は中間決算後に1度見直しが入りました。着地予測を見て予算に修正をかけることはあると思います。上司である経理管理本部長が着地予測検討して、修正を入れるべきかどうか判断をしています。
――ありがとうございます。これはOさんの感覚で構わないのですが、いわゆる中小企業さんぐらいの規模感の会社の場合、どの程度のボリューム感で予実管理をしていくのがおすすめですか?
Oさん:業種業態によって違うとは思いますが、予実管理はできれば毎月。中小企業だと季節要因などもあるかもしれませんので、少なくとも四半期では予実管理をしていくのがいいのかなと思います。PLの予実管理は繰り返していくことで予算の精度も上がっていくのではないかと思います。
――ちなみになのですが、御社は連結子会社をお持ちですが、連結子会社さんの予実管理も御社で一括して行っていらっしゃるんですか?
Oさん:はい、親会社で行っています。
――子会社さんからのデータは予定通り出てきますか?
Oさん:はい。今回できた子会社は新設分割で設立した会社なので、月次の処理も同じ経理グループで担当しています。親会社の体制で慣れているため、期日どおり資料を出してくれるので助かります。
――ありがとうございました。お話を伺っていて、スプレッドシートを上手く活用されているのが御社での工夫の特徴なのかなと感じました。
Oさん:そうですね。最後の業務確認チェックリストでも使っていますし、日々の進捗管理もスプレッドシートで行っています。
――そうすることで、やるべきことが可視化され、そのステップを踏んでいけば誰がやっても同じ業務プロセスを踏めるという。
Oさん:その通りです。
――すごいですね。
Oさん:経理は属人化しやすいじゃないですか。経理担当者としても、「この仕事は私にしかできない」という状況の方が自分の価値が上がると思っている人がいるかもしれませんが、会社としては「属人化している状態」はリスクでしかないので、誰かが急に具合が悪くなったとしても、仕事が止まらない体制にしていきたいと思っています。
そんな体制の方が、有休もとりやすいですし(笑)。
――おっしゃる通りですね。経理はベテランの方々が中心となってやっていらっしゃるケースが多いなと感じていまして、「ベテラン担当者が引退されたらどうしよう」と困っていらっしゃる会社さんも多いと思います。御社のような「まずはやることベースでプロセスを可視化していく」というスプレッドシートの話は、予実管理に限らず経理業務において他社さんも真似できることなのではないかと思いました。参考になる話をありがとうございました!