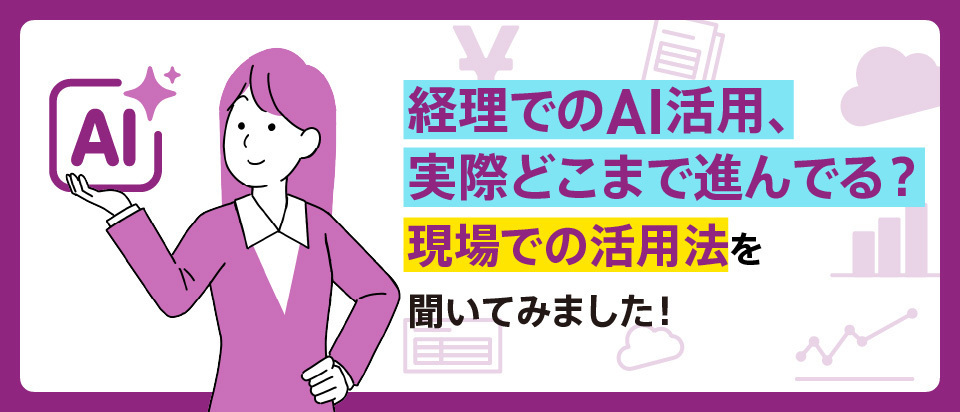何か法改正があると、それに対して適切に対応しなければならないのも経理の仕事。経理だけで対応できるものであれば良いですが、新制度に合わせた対応を現場の社員の方にお願いしなければならないこともあるため、「どうすれば円滑にいくのだろう」と悩んでいる方もいるかもしれません。
施行を見越して、システムを導入。
代表との密なコミュニケーションにより、導入開始後も大きな混乱はなし
――まずは御社の経理体制について、教えていただけますか?
Uさん:バックオフィス全体の管理を私が担っており、秘書業務、労務と各部門で担当を分け、5名前後の人員で全体を担当しています。
――今回は「電子帳簿保存法(電帳法)」と「インボイス制度」へのご対応についてお聞きしていきたいと思います。いずれも制度の導入からしばらく経ちましたが、施行直後に大変だったことはありましたか?
Uさん:施行開始を見越し、開始1年前ごろからシステムを導入して準備を進めていたため、導入直後に何か困ったということは特にありませんでした。
――素晴らしいですね!現場の社員の方に向けて、何か事前告知をするといったことはあったのでしょうか。
Uさん:いえ、社員向けには特にないですね。ただ、開始までの1年を使って、各代表とは事前にしっかりとコミュニケーションを取っていました。
特にインボイス制度に関しては、業態的に個人の方に外注することが多いため、80%控除の取り扱いについてどうするかなど、密に代表とコミュニケーションを取る必要があったんです。
――なるほど。お仕事柄個人の方とのやり取りが多いと確かに事前理解しておかないとミスや問題が起こりそうですもんね。なにか苦労はありましたか?
Uさん:個人といっても色々ありまして、例えばインフルエンサーのように、普段請求書のやり取りすらしないような方たちも含まれているんですよ。LINEで案件を決め、そのままLINEで「では、明日はこの金額でお願いします」とやり取りして終わってしまっているようなケースです。そのため、彼らに請求書を出してもらう、出してもらわない問題などは苦労した部分に入るかなと思います。
――今はもうそういった苦労はなく?
Uさん:そうですね。今はあまりもう苦労も負担もないのかなという気がします。
――今の状態に至るまで、インフルエンサーを含む個人事業主の方と、どのようなコミュニケーションを取っていったのでしょうか。ふだんやり取りしている現場の社員に伝え、社員から伝えてもらうことで上手くいくようになったという感じですか?
Uさん:ええ、そんな感じですね。経理から案内をしたい気持ちもあったのですが、業態的にインフルエンサー側のほうがパワーバランス的に強くて、コミュニケーションミスが起こると取引にも影響が及んでしまうんですね。そのため、なかなか経理側が入り込めなかったという事情もあります。
――コミュニケーションの取りやすさ的には現場の社員の方にお任せしたほうが安心ということですね。ただ、制度の理解や、それをどう伝えるかといったところは社員の方よりも経理のほうが詳しいわけですよね。インフルエンサーの方への案内を、経理として何かフォローはされたんでしょうか。
Uさん:案内文はこちらであらかじめ作っておきましたが、事前にやったことはそれぐらいですね。あとは、何か問い合わせがあったタイミングで、国税庁が出している案内など、わかりやすい図解を経理から提供したくらいかなと思います。そうしたものも活用してもらうことで、問題なく現場社員と個人の方とのコミュニケーションを取ってもらえたのかなと。
――事前に用意していたものが素晴らしかったんでしょうね。
Uさん:そんなにすごいものを作ったわけではなく、A4サイズ1枚に詳細を書いたくらいですよ。ただ、代表の考え次第なところが強いため、代表の移行にとにかく沿えるようなものを用意し、対応したという感じですね。
ただ、意向に沿うとは言いつつも、「インボイス登録をしていない個人事業主には、消費税分を全額マイナスにしたい」とおっしゃる代表者が結構多かったんですよ。これは下請法の要件に引っ掛かってしまうため、そのあたりを良い塩梅で代表の方に伝えていくことが必要でした。何社かはちょっと苦労しましたね。
――意向に沿えるのは、あくまでも法の範疇内になりますもんね。
Uさん:そうなんです。良くも悪くも癖のある代表が多いので、理解を広める、納得していただくところが1番苦労したことかもしれません。
「経理から現場社員へ」ではなく「会社として現場社員へ」
発信の形を工夫することで、社員に「ルールを守る」意識の浸透を
――経営者に理解してもらうことが必要になるのは、電帳法やインボイス制度だけの話ではなく、法改正の話すべてに対して言えることだと思います。コミュニケーションの取り方で何か工夫をされていらっしゃるんですか。
Uさん:アドバイザーとして関わっている企業に関しては、こちらが外注という立ち位置になるので、なかなか税務サポートまでは入り込めないのが実際のところなんですよね。そのため、大きな案件のところは税理士から毎月共有される情報を周知するぐらいかなと。
――それは、「第三者の専門家も守らないといけないと言ってますよ」というお墨付き的なイメージですか?
Uさん:そうですね。たとえば、2024年4月から会議費、交際費の要件が変わったんですが、そうした大きなトピックだけ共有を受け、必要に応じて代表にも案内をするといった感じです。
――最終的に制度に合わせて動くのが現場の社員の方であっても、やはりまずは代表に理解してもらうのが大事ですか?
Uさん:そう思いますね。現場の社員だけに伝え続けても、どうしてもルールを破ったり、守られなかったりするケースが多いと思うんですよ。自社はともかく、アドバイザーとして関わっている会社さんだと、代表とは密にコミュニケーションが取れないというケースもあるのですが、せめて決裁者レベルの方との連携が必要だなとは感じています。
うちの会社は、電帳法やインボイス制度への対応を含め、経理として「こうしてください」とお願いしたいことに対して、現場の社員の方の協力体制が強固なんですね。これは、単に経理を助けるためという意識があるわけではなく、会社の経営のために必要なことだという理解が現場社員に浸透しているからなんです。そうした理解を、なぜ浸透させられているのかというと、代表が現場の社員に向けてそうしたコミュニケーションを取っているからなんですね。
経理担当者が役職的に高い地位にある場合は、自分からの発信でも浸透させるのにそう苦労はしないかもしれませんが、一担当者レベルの場合は、なかなか聞いてもらえない、守ってもらえないと苦労するケースもあるでしょう。そうしたときは、発信方法を工夫して、決裁者や代表者など、何かしらの役職がある方から発信してもらう形にして、会社として守ってほしいことを伝えているんだと明確にするのがいいのではないかと思います。
――今日のテーマである電帳法、インボイス制度以外の経理の仕事にもヒントになるお話でした。今日はありがとうございました!