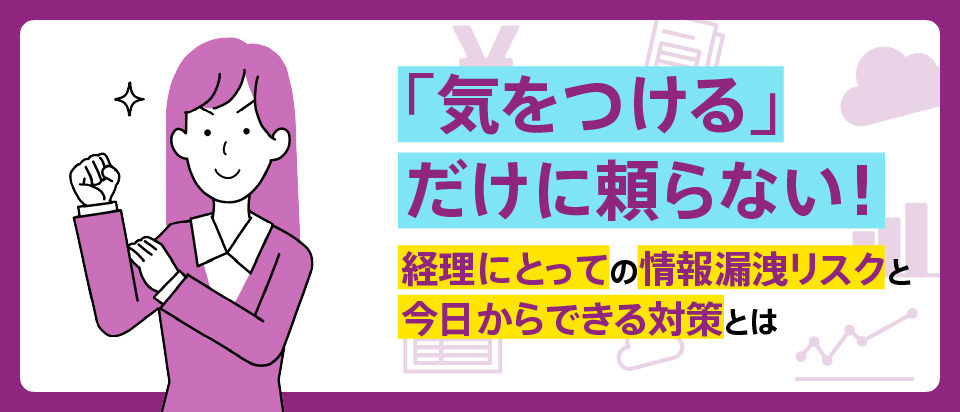2023年10月1日から始まったインボイス制度、そして2024年1月1日から完全義務化された電子帳簿保存法。いずれも、開始前には対応準備に追われたという経理の方が多いのではないでしょうか。今回は、4名で経理を担当している会社のOさん、Kさんに電子帳簿保存法、インボイス制度への対応について伺いました。
事前準備が功を奏し、「電子帳簿保存法」にすぐに対応
――まずは御社と御社の経理体制について、簡単にご紹介いただけますか?
Oさん:弊社は社員数100名以上の上場企業です。経営管理本部長のもと、経理は4名で担当しています。
――ありがとうございます。では、さっそく今回のテーマである電子帳簿保存法、インボイス制度への御社の対応について伺っていきたいと思います。どちらも施行されてしばらく経ちましたが、ご状況はいかがですか?
Oさん:電子帳簿保存法については、使っているシステムに、取引先や費用計上月、金額、費用科目などの情報を入力し、PDFで請求書など必要書類を添付して申請してもらうようにしているため、そこで一通り検索できるようになっています。本来であれば、タイムスタンプやファイル名称を変更しての保存も必要なのかなと思っていますが、一旦はこれでいいかなという感じですね。
――事前に準備をされて臨まれたということですか?
Oさん:そうですね。当時は今ほど経理メンバーが多くはなかったので、経営管理本部長と私のふたりで相談しながら進めました。
――今の形に落ち着くまで、何か苦労されたことはありましたか?
Oさん:経理側では特に大きな苦労はなかったですね。ただ、事業部側の負担はあるのかなとは思います。今も受け取った請求書を一旦すべてPDFにして「請求書承認申請」をしていただいているので、今後その手間は省いてあげたいと思います。
――確かに事業部側に負担がありますよね。「PDFにして添付してください」など、施行開始による変更について事業部の方たちにお伝えした際、皆さんの反応はいかがでしたか?
Oさん:弊社の事業部の方たちは、ありがたいことに非常に経理グループに対して協力的なので、電子帳簿保存法の開始に関しても特に困ることなく協力してもらえました。システムでの申請自体は電子帳簿保存法の施行前から行っていたため、変更点は「請求書をPDFで添付する」だけだったので、比較的スムーズだったのかなと思っています。
――改めて、整備することが重要なことがよくわかりました。更にアップデートしたいことなどありますか?
Oさん:事業部の負担を軽減するために、請求書の受け取りサービスのようなものを導入したいと思い検討を始めているところです。
――素晴らしいですね。ご導入が決まりましたら、ぜひまたお話を伺いたいです。
インボイス対応もシステム導入で解決。社員と円滑にやり取りできる関係性づくりも大切
――次はインボイス制度について伺いたいです。こちらで何か困ったことはありましたか?
Oさん:インボイス導入時に取引先様に確認し、会計システムの「取引先」にインボイス番号の登録をしていますので、仕訳の計上で困ることはあまりないです。また、月次が終わったタイミングで適格検査をして、免税業者の方が適格請求書発行事業者になっていたり、適格請求書発行事業者の方が失効されていたりといった変化を確認するようにしています。
電子帳簿保存法よりもインボイス制度への対応のほうが、少し手間がかかっている気がしますね。弊社は法人カードを使って海外ツールも結構使っているため、その分の請求書や領収書、インボイスに関する書類を保存していただくよう事業部に依頼しています。毎月その確認には少し時間がかかっています。
――確かに複雑そうですね。手間だと感じられている部分に関して、「こうすればもっと良くなる」と思っていらっしゃることはありますか?
Oさん:今思い浮かぶのは、事業部の方にきちんと書類を保存してほしいということぐらいですね。チェック時に証憑がないこともありますので…
証憑の保存以外で、経理でフォローできるところに関しては、こちらでお手伝いしながら対応しています。たとえば経費精算時に電車代など公共交通機関の特例に関しては、使っているシステムのなかに「公共交通機関特例」という区分を設けていまして、そこを選んでもらうようにしています。仕訳データ出力時にその区分も一緒に出てくるよう設定していますので、経理で確認するときに、区分が入っていなければこちらで追加しますし、毎回抜けているなという方には、個別に「次からちゃんと入れてね」と繰り返し伝えるようにしています。その結果、もれなく記入いただけるようにはなってきたと思います。
――事業部側の人間としては耳が痛いといいますか、申し訳ないなと感じる話です……。
Oさん:いえいえ。皆さん忙しいなかで請求書の承認申請や経費精算を期日通り出してくださっているのはありがたいと思っています。申請さえ漏れなくだしていただければ、こちらでもフォローはできますので大丈夫です。
――ご本人に伝えるときは、どう伝えるようにしていますか?
Oさん:そうですね。ただ「こうしてください」と伝えるだけではなく、できるだけその対応が必要な理由をちゃんと説明するようには心がけています。
――その繰り返しで、皆さんの対応力も上がってきていると感じられますか?
Oさん:はい。先ほどの繰り返しになりますが、皆さん協力的なので、きちんと対応してくださっているなと感じますね。
――ちなみに、経費を申請される方は何人ぐらいでしょうか。
Oさん:毎月、定期的に出している方は40~50名ぐらいですね。
――なるほど、結構な人数ですね。細かくフォローされているなと感じましたが、フォローされるときはテキストコミュニケーションがメインなのでしょうか?
Oさん:はい。社内チャットで依頼するケースが多いです。でも、全員同じフロアにいるので、通りがかったときに「経費精算、今日が締めですよ~。」と声をかけたりすることもありますよ。
――皆さんと顔見知りでいらっしゃるんですね。
Oさん:まだ120、130名ぐらいの会社なので、現場の方とそう距離感があるわけではないですね。経理は何かと皆さんにお願いすることが多い立場で、皆さんにやってもらえないと自分たちが困るので、何かを伝えるときは威圧的にならないよう心がけています。
――それはとても大事なことですね!きちんと行われていらっしゃるのが素晴らしいです。Oさんのお人柄も一役買っているのではないかと思います。
Oさん:ありがとうございます。そうだといいのですが、実はすごく圧を感じられているかもしれません(笑)。
――実際にすごく上手くいってらっしゃるので、そんなことはないのだと思います。先ほど「同じフロアにいる」とおっしゃっていましたが、出社される方は多いですか?
Oさん:3分の1くらいはリモートワークですね。開発の方はオンラインが多いなど、部署によって変わってきます。とはいえ、開発部とは月に1回はミーティングなどもありますし、
定期的に“グループフェス”といって、今月は管理部と事業部。次の月は開発部と管理部など、いろいろな部門同士で、顔を合わせて食事やお酒を楽しみながら話ができる機会があるんです。それが功を奏して、ちょっとした相談がしやすくなったり、話しかけやすくなったりというところはあると思います。
――いいですね、対面コミュニケーションを取る機会があるからこそ、現場の方とのやり取りも上手くいってらっしゃるのかなと思いました。ここまで、電子帳簿保存法とインボイス制度への対応や苦労について伺ってきましたが、改めて御社が上手くいっている要因について、Oさんはどう見ていらっしゃいますか?
Oさん:そうですね、やっぱりある程度はシステムを使うしかないということでしょうか。交通費の特例も、システムでデータを出力して取り込めば、漏れを防げますし、電子帳簿保存法への対応も自動のタイムスタンプ機能を活用できるでしょうし。請求書の受け取りサービスも導入できれば、すごく便利になるんだろうなという気がしています。
――今日はありがとうございました!