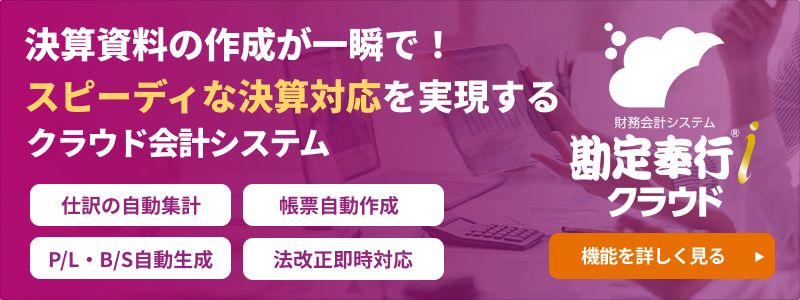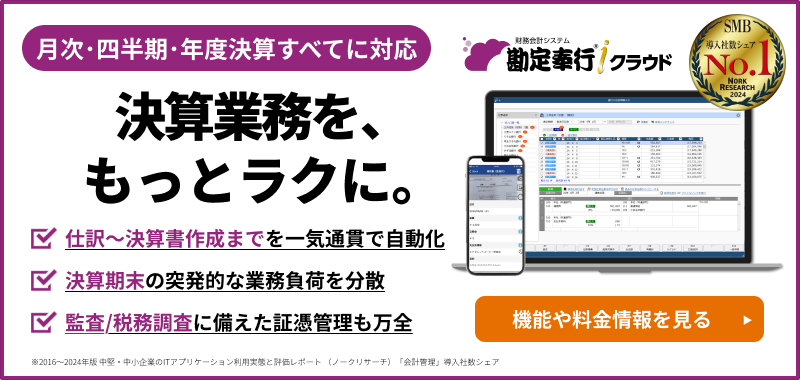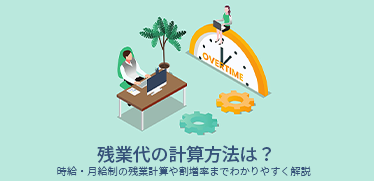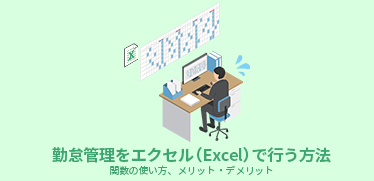

中間決算とは、企業が事業年度の途中で財務状況や経営成績を確認し、必要な会計処理や税務申告に備えるために実施する決算業務のことです。上場企業は半期報告書等による情報開示が義務づけられており、中小企業では資金繰りの確認や経営戦略の見直しに役立てられています。
本記事では、中間決算の目的や流れ、業務を円滑に進めるための具体的なポイントについて詳しく解説していきます。
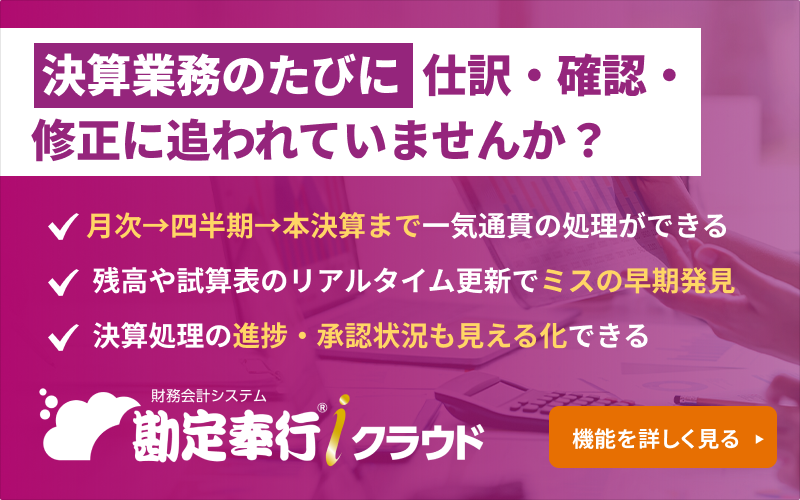
目次
中間決算とは?
中間決算とは事業年度の途中で実施する決算であり、財務諸表の作成や経営状況の確認を目的としています。本決算と同様に損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表を作成しますが、法的な義務は企業の区分によって異なります。ここでは、中間決算の定義と特徴について整理します。
●中間決算の定義
中間決算とは、企業が本決算を行う期末を迎える前、具体的には事業年度の中間時点で財務状況や経営成績を明らかにするために実施する決算手続きのことです。通常は、年次決算と同様の会計基準に従って処理されます。
作成する書類は中間損益計算書・中間貸借対照表・中間キャッシュ・フロー計算書の3つで、これらにより、一定期間における収益性や安全性、資金の流れといった経営指標を数値で可視化できます。正確な帳簿記録と勘定科目の適切な設定を通じて、経営の現状を把握し、今後の意思決定に役立つ情報を得ることができる重要な業務です。
●中間決算を行う時期
中間決算は、企業の事業年度の半期終了時点で行います。たとえば、事業年度が4月1日から翌年3月31日までの企業であれば、9月末が中間決算日となります。会計期間の設定は企業ごとに異なりますが、法人税や消費税の予定申告に備え、あらかじめ計算根拠となる決算数値を確定させるためにも、半期終了時点での実施が必要です。
●中間決算を実施する目的
中間決算には、大きく3つの目的があります。まず、半期を終えたタイミングでの財務状況を把握し、経営戦略の見直しや資金繰りの調整に役立てることです。次に、株主や取引先、金融機関といったステークホルダーに対し、経営の透明性を示すことも目的です。
さらに、前期に一定額以上の法人税や消費税を納付している企業は中間申告に向けて仮決算を行う必要があるため、その準備というも目的もあります。中間申告の納税額は、原則として前期の税額の半額が目安であり、法人税・消費税の両方が対象です。
●中間決算の計算方法
中間決算では、対象期間に該当する売上や費用を集計し、中間損益計算書・中間貸借対照表・中間キャッシュ・フロー計算書を作成します。この際、売掛金や買掛金、棚卸資産などの残高確認を行い、発生主義に基づいた会計処理を徹底することが重要です。
また、減価償却や引当金の計上といった決算整理仕訳も必要となるため、固定資産台帳や帳簿類を基に正確な数値を反映させます。さらに、税効果会計を適用する場合は法人税等の見積額も算出し、税引後利益までを確定させます。
決算の主な種類
決算とは、企業の一定期間における経営成績や財務状況を明らかにし、財務諸表としてまとめる会計手続きのことです。中間決算もその一種であり、事業年度の途中で実施される重要な決算の一つです。ここでは、本決算をはじめとするさまざまな決算の種類について整理し、それぞれの特徴を解説します。
●【期間別】決算の種類
期間で分けた決算の種類は大きく4つに分かれます。
・本決算
企業の事業年度の終了時に行うのが本決算で、一般的な事業年度は1年間です。損益計算書や貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表を作成し、年間の経営成績と期末時点での財務状態を確定させる最も重要な決算業務です。
・中間決算(半期決算)
中間決算は、企業の事業年度の中間時点で実施される決算で、「半期決算」とも呼ばれます。本決算と同様に、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成し、半期終了時点での経営成績と財務状態を明らかにします。
上場企業では、金融商品取引法に基づく半期報告書の提出義務を果たすために中間決算を実施するほか、資金繰りや経営管理の見直しに活用する企業も多く、経営の透明性向上にも貢献します。
・四半期決算
四半期決算は、3か月ごとに年4回実施されます。現在、金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出義務は廃止されていますが、証券取引所の規則により、上場企業に対しては四半期決算短信の開示が求められています。経営状況の迅速な把握や投資家に対する情報開示体制の一環として重要です。
・月次決算
月次決算は、毎月の取引を締めて集計する内部管理用の決算で、法的な実施義務はありません。月次決算を行うと売上や費用、利益の動向を月単位で把握できるため、資金繰りの調整や経営判断の迅速化に役立ちます。
財務諸表の作成範囲や精度は企業によって異なりますが、いずれにしても本決算や中間決算の精度向上にもつながるといえます。
●【対象会社の数別】決算の種類
対象会社の数によって「単独決算」と「連結決算」の2つに分かれます。
・単独決算
単独決算は、親会社や子会社といった関係会社を含めず、企業単体で行う決算です。「単体決算」または「個別決算」とも呼ばれ、中小企業や非上場企業で広く採用されています。
当該企業のみの売上や費用、資産、負債などを対象に財務諸表を作成し、法人税申告や資料としての金融機関への提出、社内管理などに活用されます。連結決算とは異なり、会計処理が比較的シンプルで管理しやすい点も特徴です。
・連結決算
連結決算は、親会社と子会社を1つの企業グループとしてまとめて行う決算です。グループ全体の経営実態を明らかにするために行われ、具体的には親会社と子会社間の内部取引や債権・債務を相殺し、外部との取引のみを財務諸表に反映させます。
作成される連結財務諸表には、連結損益計算書や連結貸借対照表などが含まれます。上場企業には原則として連結決算が義務付けられており、M&Aを行った企業や中堅企業でも導入が進んでいます。
中間決算の流れ
中間決算は、記帳内容の確定から始まり、棚卸や決算整理仕訳、財務諸表の作成といった一連の手続きを経て、最終的に中間申告と納税に至ります。ここでは、中間決算を円滑に進めるための具体的なステップを、5つに分けて解説します。
●Step1.記帳の確定
中間決算の第一歩は、半期分の取引についての記帳をすべて終わらせ、試算表を作成することです。現金出納帳・仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を整理し、必要に応じて記帳漏れや誤記の修正を行います。
これによって正確な残高を確認できたら、試算表として数値を一覧化します。一覧化することで、企業の収益と費用の大まかな構造を把握することが可能です。
●Step2.預金残高の確認と棚卸の実施
次に、帳簿と実際の残高にズレがないかを確認するため、通帳やWeb明細と突き合わせて預金残高をチェックします。必要に応じて残高証明書を取得し、差異が見つかった場合は原因を調べて修正仕訳を行います。
併せて、棚卸資産については実地棚卸を実施し、商品や原材料などの在庫数と評価額を把握します。帳簿と実数に差がある場合は、その内容を反映して評価額を調整することが重要です。
●Step3.中間決算整理仕訳の実施
中間決算では、期間損益を正しく算出するために整理仕訳を行います。まず、固定資産について半期分の減価償却費を計算し、台帳に基づいて償却費を計上します。さらに、未収収益や未払費用、前受収益や前払費用といった経過勘定を整理し、発生主義に則った処理を行います。
貸倒引当金や賞与引当金などの見積計上も必要です。これらの整理仕訳を行うことで、実態に即した損益計算が可能となり、決算の精度が高まります。
●Step4.財務諸表の作成
整理仕訳が終わったら、修正後の試算表を基にした中間財務諸表の作成です。まずは中間損益計算書によって半期の売上高や費用、利益を集計し、経営成績を明確に把握します。
続いて、中間貸借対照表によって資産・負債・純資産を分類し、期中の財務状態を可視化していきます。さらに、中間キャッシュ・フロー計算書を用いて現金の流れを整理することで、資金の過不足や運用状況を具体的に確認することが可能です。
●Step5.中間申告と納税
中間決算の手続きが完了したら、法人税や消費税の中間申告と納税を行います。法人税の中間申告では、前期の確定税額の半額を納付する「予定申告」と、中間決算に基づいて実際の税額を算定する「仮決算による申告」のいずれかを選択できます。仮決算を選べば、実態に即した税額での納付が可能です。消費税についても同様に、予定申告か仮決算かを選びます。
いずれの場合も、申告書の作成と提出は所定の期限内に完了させ、税金の納付も期日を守って行う必要があります。期日を過ぎると延滞税や加算税を課されるおそれがあるため、事前のスケジュール管理が重要です。
中間決算をスムーズに行うポイント
中間決算を効率的に実施するためには、事前の準備と適切な管理体制の構築が欠かせません。目的の明確化から始まり、日常的な記帳管理、現実的なスケジュール設定、そして会計システムの効果的な活用まで、複数の要素について総合的に検討する必要があります。ここでは、中間決算をスムーズに進めるための具体的なポイントを4つの観点から解説します。
●目的の明確化
中間決算は、法定義務のない企業にとっては任意の業務であるため、実施する際は明確な目的を設定することが欠かせません。目的が曖昧なまま進めてしまうと、経理担当者に余計な負担がかかり、業務効率が下がるおそれがあります。
たとえば、経営状況の把握、金融機関への資料提出、予算修正の判断材料など、具体的な活用目的を事前に明確にしておけば、必要な作業の範囲と精度も自然に定まり、効率的な決算実施が可能となります。さらに、経営陣と経理部門が目的を共有することで、現場との連携が強化され、実務も進めやすくなるはずです。
●記帳と証憑の保存
中間決算を正しく進めるには、日々の取引内容をきちんと記録し、それを裏付ける書類を整理しておくことが大切です。たとえば、売上や仕入れ、経費などの取引があれば、その都度すぐに帳簿に記入します。また、領収書や請求書、契約書などの書類も取引ごとにわかりやすくまとめて保管しましょう。
月末や決算の前には、請求し忘れや支払い漏れがないかを確認し、必要に応じて取引先に問い合わせることも重要です。また、書類をデータとして保存すれば探しやすくなり、決算作業もスムーズになります。
●スケジュールの策定
中間決算を円滑に進めるには、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。特に月次決算を行っていない企業では、半年分の取引を一度に集計する必要があるため時間を要することがあります。
まずは、帳簿の記載内容の確定や財務諸表の作成、申告書の提出など、必要な作業を洗い出し、それぞれに割ける期間を設定します。残高証明書の取得や税理士との調整など、外部との連携が必要な作業は早めに対応し、申告期限の1週間前には完了できるよう準備しましょう。
●会計システムの活用
中間決算では、会計基準や税法に沿った処理が求められるため、これらがすでに組み込まれた会計システムを活用することで業務の効率化とミスの防止を図れます。多くのシステムは、財務諸表や申告書の自動作成、自動仕訳、消費税の自動計算などにも対応しており、日常の取引の記帳から決算書類の作成までをスムーズに行えるでしょう。
さらにクラウド型を選べば、税理士との情報共有もスムーズになります。導入時には、自社の業務に適した機能を備えているかを見極めることが重要です。
中間決算に関してよくある質問
中間決算の実施を検討するにあたっては、「本決算と同じような手続きが必要なのか」「中小企業でも実施すべきか」「どの程度の費用がかかるのか」など、実務上の疑問が多く挙がります。特に初めて対応する担当者にとっては、制度上の位置づけや仮決算との違いを理解しておくことが欠かせません。ここでは、中間決算に関する代表的な4つの質問について、制度と実務の両面から簡潔に解説します。
- 中間決算に必要な手続きは本決算と異なる?
-
中間決算でも、本決算とほぼ同様の手続きが求められます。一部は省略できますが、仮決算による中間申告を行う場合には、正確な書類を税務署に提出する必要があるため、精度の高い作業が求められます。実際の経理業務には、現金出納帳や預金通帳の残高照合、棚卸表の作成、売掛金・買掛金・未収入金・未払金・借入金といった各勘定科目の残高確認、固定資産台帳のチェック、帳簿と実際の残高の突き合わせなどが含まれます。
こうした作業を通じて、金額の正確性を確保し、財務の健全性を確認するための基礎情報を整えることが求められます。中間決算を正確に行うには、これらの資料や数値を事前に整備しておくことが不可欠です。
- 法人に中間決算は必要?
-
法人における中間決算の必要性は、企業の属性によって異なります。上場企業は金融商品取引法によって半期報告書の提出が義務づけられているため、中間決算は必須です。一方、非上場の法人には法的義務はありませんが、前期の法人税が20万円超または消費税が48万円超の場合には中間申告が必要です。
また、仮決算を選ぶ場合も、中間決算として財務諸表を作成し、それに基づいて中間申告書を税務署に提出する必要があります。さらに、経営状況の可視化を目的として、任意で中間決算を行う企業もあります。法的義務の有無だけを基準にせず、自社の状況や必要性に応じて実施の是非を検討することが重要です。
- 中間決算にかかる費用の目安は?
-
中間決算にかかる費用は、税理士や会計事務所などの外部に依頼するか、自社で対応するかによって異なります。税理士にスポットで依頼する場合は10万円〜25万円程度が相場であり、年間契約に中間決算対応が含まれている場合は追加費用がかからないこともあります。企業の規模や取引の複雑さ、書類作成の範囲によっても費用は変動します。
また、自社で対応する場合も、人件費や帳票類の印刷費、残高証明書の発行手数料などが発生します。特に初めて中間決算を実施する企業では担当者が作業に手間取るおそれがあるため、事前に外部委託の見積もりを取得し、総合的なコスト比較を行うことが重要です。
- 中間決算と仮決算の違いは?
-
中間決算は、事業年度の途中で経営状況を把握するために行う決算処理全般を指し、財務諸表の作成などを含みます。一方、仮決算は中間申告の方法の一つで、期中の実際の数値に基づいて法人税などを算出・申告するものです。
なお、中間申告には「予定申告」と「仮決算による申告」の2種類があります。予定申告では前期税額の半額を納めますが、仮決算による申告の場合は半期時点の利益額に応じて納税額を計算するため、業績が低調な場合には納税額を抑えられる可能性があります。このように、中間決算は経営管理のための処理、仮決算は税務申告のための手続きであり、役割と目的が異なるため、区別して理解することが重要です。
中間決算とは何かを理解し、効率的な実施を目指そう
中間決算とは、企業が事業年度の中間時点での経営状況を把握し、ステークホルダーへの情報開示や税務申告に備える重要な決算です。適切な準備と管理体制により、中間決算の業務負担を軽減しながら、経営判断に役立つ有益な情報を得ることが可能となります。
中間決算を円滑に進めるには、会計システムの活用が不可欠です。たとえば、勘定奉行iクラウドでは、決算回数を「年1回」「年2回(中間決算)」「年4回(四半期決算)」から選択でき、決算期ごとに決算報告書を自動作成できます。消費税の中間申告にも対応しており、仮決算による申告書作成から電子申告・電子納税までを一貫して行えます。
より広範な業務領域をカバーしたい中堅・成長企業には、SaaS型ERP「奉行V ERPクラウド」の導入も効果的です。各種業務システムと連携しやすく、データの自動集約と柔軟な活用が可能なため、経営状況の可視化と意思決定の迅速化につながります。
中間決算の効率化を図りたい企業は、これらの「奉行シリーズ」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。システム活用によって負担の大きい決算業務を省力化し、経営資源をより付加価値の高い業務に集中させることが可能になります。
関連リンク
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!