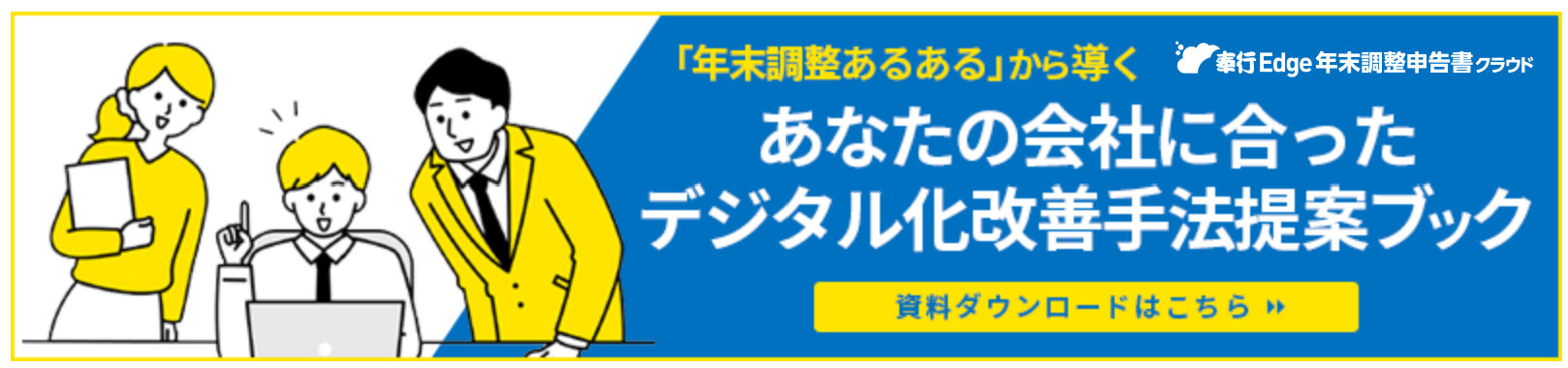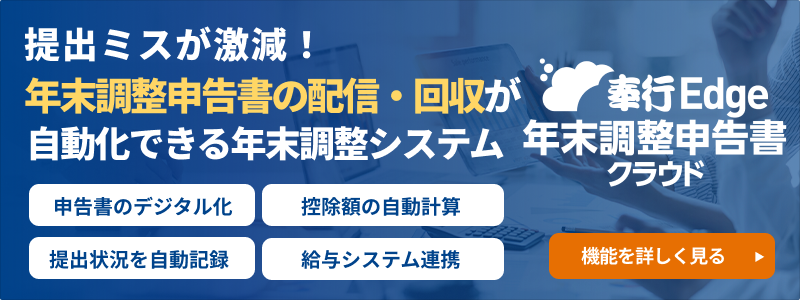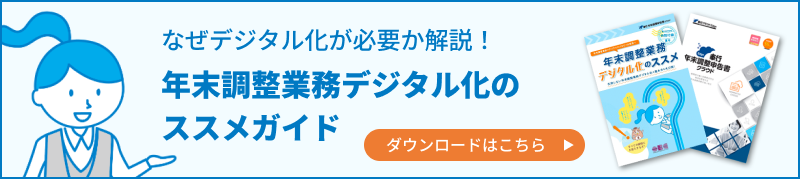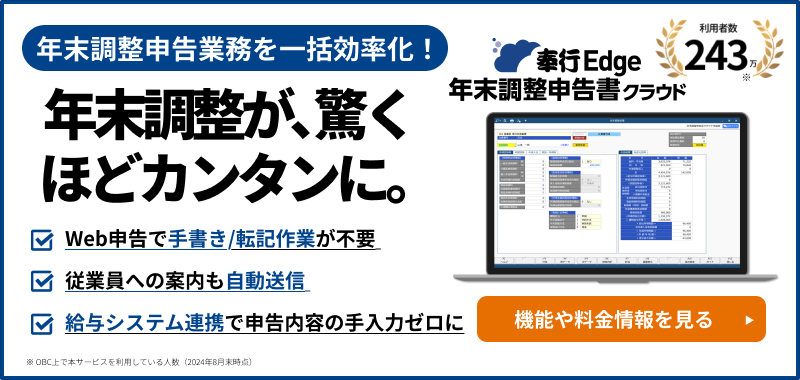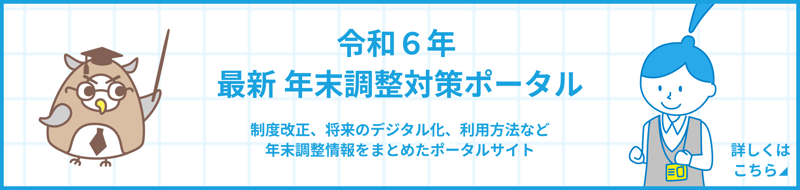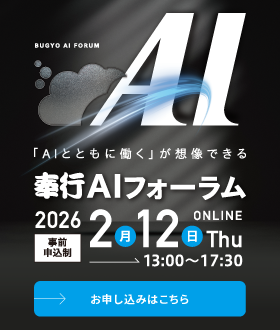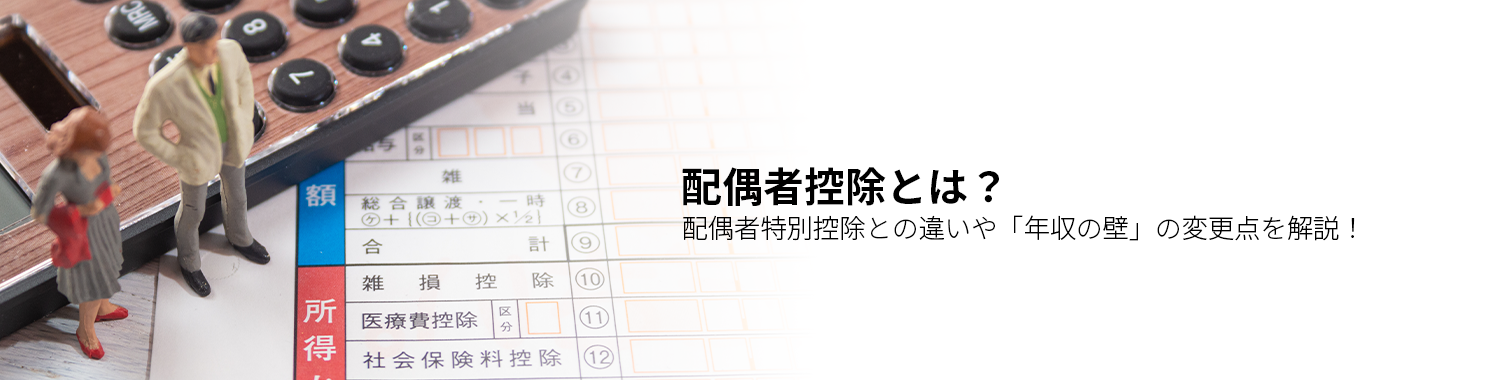
配偶者控除や配偶者特別控除は、収入や家族構成によって適用要件が細かく分かれており、申告内容を正しく理解していないと控除漏れや記入ミスにつながります。2025年には「年収の壁」の見直しが決定され、これに伴い控除対象となる条件がすでに変更されたものもあります。
実務担当者は、改正内容とともに控除の適用要件を把握し、ミスのない年末調整・申告対応を行う必要があります。本記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の制度の違いや改正ポイント、手続きの方法、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
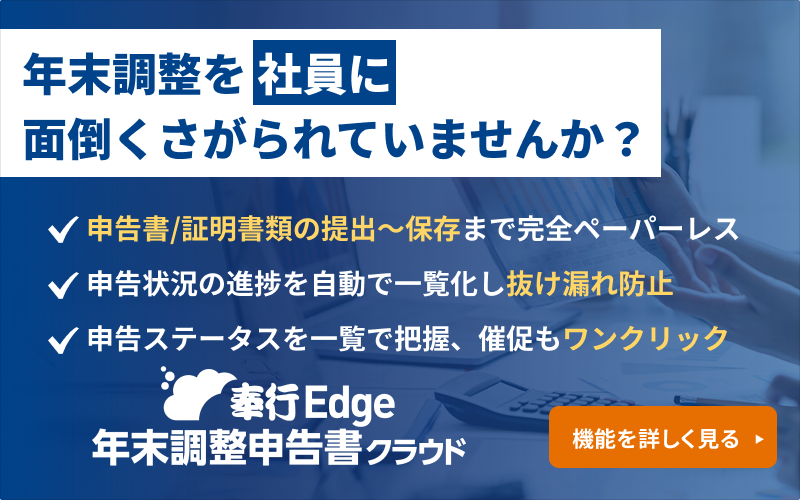
目次
- 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
- 2025年から配偶者控除・配偶者特別控除が変わる背景
- 配偶者控除・配偶者特別控除に関わる4つの「年収の壁」
- 税金・社会保険にもある「年収の壁」に注意
- 配偶者控除・配偶者特別控除の申請手続きと実務ポイント
- 配偶者控除・配偶者特別控除の申請時に確認すべき実務上の注意点
- 配偶者控除・配偶者特別控除の実務でよくある質問
- 配偶者控除・配偶者特別控除の年末調整を支えるクラウドサービスの活用
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除・配偶者特別控除は、どちらも「年収が一定額以下の配偶者がいる場合に扶養する側の所得税が減額される制度」のことをいいます。
どちらも、従業員本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみなら年収1,195万円以下、ただし所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円以下)であることが前提であり、配偶者に対する条件によって「配偶者控除・配偶者特別控除のどちらを適用できるか/できないか」が決まります。どちらかを適用できる場合、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と対象となる配偶者の合計所得金額の組合せによって、控除される金額が決まります。
●配偶者控除とは?
2025年の税制改正により、配偶者控除は「配偶者の年収(給与収入)が123万円以下」の場合に適用されることになりました。配偶者に給与以外の所得がある場合は、合計所得金額が58万円以下であることが条件です。
対象となるのは民法上の配偶者であり、生計を一にしている必要があります。青色申告者や白色申告者の事業専従者に該当する配偶者は対象外です。また、控除額は、納税者本人の合計所得金額や扶養状況によって変動します。
●配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除は、配偶者の年収(給与収入)が123万円を超え、201万6,000円未満の場合に適用される所得控除制度です。配偶者控除の対象から外れる年収帯であっても、条件を満たせば段階的に控除を受けられます。配偶者の年収160万円以下かつ納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば満額(38万円)、160万円超から201万6,000円未満では、収入が増えるにつれて控除額が徐々に減少します。
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。その他の要件は配偶者控除と同様で、青色申告者や白色申告者の事業専従者に該当する配偶者は、この制度の対象外です。
2025年から配偶者控除・配偶者特別控除が変わる背景
2025(令和7)年度から、配偶者控除および配偶者特別控除の適用条件が見直されます。これは、政府が公表した「令和7年度税制改正大綱」において、所得税に関する扶養控除制度の見直しが示されたことによります。これまでの制度では、配偶者の年収が150万円を超えると控除額が減少していましたが、2025年からはその基準が見直され、年収160万円以下の範囲でも満額の控除が受けられるようになりました。
この見直しにより、パートやアルバイトなどで一定の収入がある配偶者でも、より広い範囲で控除を受けることができます。制度の実務を担う担当者は、従業員への説明資料の更新や、年末調整書類のチェック項目の見直しなど、対応準備を進めておく必要があります。
【出典】財務省:令和7年度税制改正の大綱の概要
配偶者控除・配偶者特別控除に関わる4つの「年収の壁」
配偶者控除や配偶者特別控除を正しく適用するには、所得控除の適用可否や制度の対象となるか否かが変わる「年収の壁(年収基準のボーダーライン)」を理解することが欠かせません。2025年の税制改正では、「103万円の壁」が「123万円の壁」に、「150万円の壁」が「160万円の壁」に見直されました。
これらの変更は従業員の働き方や控除対象の判断に直結するため、年末調整の実務を担う担当者には制度理解と運用対応の両面が求められます。ここでは、配偶者控除・配偶者特別控除に関わる4つの年収の壁について解説します。
●123万円の壁―「配偶者控除を受けられるか否か」(旧:103万円の壁)
2025年の税制改正では、配偶者控除の年収基準が見直され、従来の「103万円の壁」は「123万円の壁」へと引き上げられました。これは、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ10万円ずつ増額されたことに対応した変更です。
配偶者の年収が123万円以下であれば、納税者は最大38万円の配偶者控除を受けることができます。123万円を超えると配偶者控除の適用外となりますが、一定の範囲内であれば配偶者特別控除の対象になります。この改正により、配偶者控除が適用される年収の上限が引き上げられたため、対象従業員の年収確認や申告書の記載内容をより丁寧にチェックする必要があります。
●160万円の壁—「配偶者特別控除を満額適用できるか否か」(旧:150万円の壁)
2025年の税制改正により、配偶者特別控除で満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収上限が、従来の150万円から160万円に引き上げられました。配偶者の年収が160万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除を受けることが可能です。
160万円を超えると控除額は段階的に減少しますが、上限額が引き上げられたことで、就業調整を意識せずに働く配偶者も増えると見込まれます。担当者は、配偶者の年収次第で控除額が変動する点に留意し、対象者の判定や申告内容の確認を丁寧に行う必要があります。
●201万円の壁—「配偶者特別控除を受けられるか否か」
配偶者の年収が201万6,000円以上になると、配偶者特別控除は一切受けられなくなります。これは、給与所得控除を差し引いたあとの配偶者の所得が、控除を受けられる上限である133万円を超えるためです。この上限は2025年の税制改正でも変更されておらず、従来どおり維持されています。
配偶者の年収がこの壁に近い場合、控除額は段階的に減少するため注意が必要です。控除の有無だけでなく、配偶者の収入増が世帯全体の手取りや保険料負担に与える影響についても、あらかじめ確認・説明できるようにしておくことが重要です。
●1,000万円の壁—「配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるか否か」
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも適用されなくなります。この所得制限は、2025年の税制改正後も変更されていません。給与収入のみのケースでは、合計所得金額が1,000万円を超えるかどうかの目安は、年収1,195万円(所得金額調整控除がある場合は1,210万円)となります。
この所得制限は高所得者に対する優遇を抑える目的で設けられました。担当者は従業員の所得額を把握したうえで、控除適用の可否を見落とさないよう注意が必要です。
税金・社会保険にもある「年収の壁」に注意
配偶者控除・配偶者特別控除以外にも、働く人が意識すべき「年収の壁」が存在します。これらは、住民税や所得税がかかり始める年収の目安や、社会保険への加入が必要になる基準を示しており、働き方や手取り収入に直接影響します。担当者は、これらの基準についても把握し、従業員からの相談に落ち着いて対応できるようにしておくことが大切です。
●税金に関わる年収の壁
税金に関わる年収の壁としては、以下の「110万円の壁」「123万円の壁」の2つが挙げられます。
・110万円の壁(2026年度分の住民税以降。それまでは100万円の壁)
年収が110万円を超えると、住民税の課税対象となります。住民税には、所得に関係なく一律で課される「均等割」が含まれているため、年収が比較的少ない場合でも課税されることがあります。なお、均等割の金額や非課税の基準は自治体によって異なる点にも注意が必要です。
ただし、未成年で前年の給与収入が204万4,000円未満の場合など、非課税となる特例も設けられています。この「110万円の壁」は住民税の課税基準に関するものであり、配偶者控除の適用条件とは別制度です。制度の混同を避けるためにも、担当者はそれぞれの趣旨と影響を正確に把握しておきましょう。
・160万円の壁(旧:103万円の壁)
かつては、年収103万円を超えると本人に所得税が課税されていました。これは配偶者控除の「103万円の壁」と混同されがちですが、本人が課税対象か否かの基準であり、別の制度です。
2025年の税制改正により、年収200万円以下の基礎控除額 が引き上げられ(95万円)、給与所得控除額が10万円引き上げ(65万円)られた結果、所得税の課税開始の年収目安が160万円に変更されました。担当者は、配偶者控除との混同を避け、制度ごとの内容を整理して対応する必要があります。
●社会保険に関わる年収の壁
次に、社会保険に関わる年収の壁としては、以下の「106万円の壁」「130万円の壁」の2つが挙げられます。
・106万円の壁
従業員が51人以上いる企業など、社会保険の適用事業所に勤めるパート・アルバイトが、週20時間以上かつ月額8万8,000円以上の報酬を得る場合、厚生年金や健康保険への加入が義務づけられます。年収に換算するとおおむね106万円以上であり、この金額を超えると従業員自身が社会保険料を負担することになるため、手取り額が減少します。なお、この基準は2026年10月に撤廃される予定であり、今後の動向にも注意が必要です。
・130万円の壁
配偶者が扶養に入れる年収の上限が130万円です。これを超えると扶養から外れ、本人が国民健康保険や厚生年金に加入し、保険料を負担することになります。制度の違いによって税金の控除とは別に判断されるため、年末調整や労務相談の際には留意が必要です。
●(参考)年収の壁と制度への影響一覧
この表は年収順に「どの壁を超えると何が起きるか」をまとめたものです。税金・社会保険・所得控除などの影響を一覧できます。ぜひ参考にしてください。
| 壁の金額 | 主な影響内容 | 該当制度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 所得税課税(旧基準) | 所得税(旧制度) | 2025年改正で実質廃止 参考として記載 |
| 106万円 | 社会保険強制加入 (勤務先による) |
社会保険(106万 円の壁) |
従業員数51人以上などの条件で厚生年 金等に加入義務発生 |
| 110万円※ ※2026年度分の 住民税以降 |
住民税(所得割)が課税 | 地方税(住民税) | 多くの自治体で住民税が発生 非課税枠あり(自治体差あり) |
| 123万円 |
配偶者控除の対象外に/ |
配偶者控除/扶養控除 | 2025年改正で引き上げられた 「新しい103万円の壁」 |
| 130万円 | 扶養から外れる(保険料自己負担) | 社会保険(130万円の壁) | 国保や国民年金に自分で加入が必要 |
| 150万円 | 特定親族特別控除の満額対象 外に |
特定親族特別控除 |
居住者と⽣計を⼀にする19歳以上23歳 |
| 160万円 | 所得税課税開始/配偶者特別控除の満額対象外に | 所得税/配偶者特別控除 |
所得が増えると配偶者特別控除額が段階的に減少 |
| 201万6千円 | 配偶者特別控除の対象外に | 配偶者特別控除 | 所得133万円超(給与換算201万6千円以上)で対象外 |
| 1,000万円 (本人) |
配偶者控除・特別控除の適用不可 | 納税者本人の制限 | 給与収入換算で1,195万円超なら不可 |
配偶者控除・配偶者特別控除の申請手続きと実務ポイント
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、年末調整または確定申告による申請手続きが必要です。申請方法は納税者の雇用形態に応じて異なり、会社員は勤務先での年末調整で、個人事業主は確定申告で手続きを行います。申請書類の記載内容に誤りがあると控除が適用されない可能性があるため、担当者には従業員への説明と申告書の確認を丁寧に行うことが求められます。
●年末調整で申請する場合
年末調整は、給与所得者である従業員がその年の所得税額を確定させる手続きであり、配偶者控除・配偶者特別控除もこのタイミングで申請します。該当する控除を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への記載が必要です。
この申告書では、納税者本人の所得は「基礎控除申告書」の欄に、配偶者の合計所得金額は「配偶者控除等申告書」の欄にそれぞれ記載します。配偶者に給与以外の所得(事業所得・不動産所得・配当所得など)がある場合、そのすべてを合算して記載する必要があります。

出典:国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
控除の適用要件を満たすかどうかは記載された合計所得金額で決まるため、申告内容に誤りがないか確認を徹底しましょう。申告書は、勤務先で定められた提出期限までに提出する必要があります。
●確定申告で申請する場合
確定申告は、納税者が個人事業主や自営業者である場合の申請方法ですが、会社員でも医療費控除や住宅ローン控除などを申請する際に併せて行うことができます。配偶者控除や配偶者特別控除の申請には、確定申告書第一表の所得控除「配偶者(特別)控除」欄への控除額の記入と、第二表「配偶者や親族に関する事項」欄への配偶者情報(氏名、生年月日、マイナンバー等)の記載が必要です。申告書の記載ミスがあると控除が適用されないため、記入内容の確認を怠らないよう注意が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の申請時に確認すべき実務上の注意点
配偶者控除・配偶者特別控除の制度は、適用条件が複雑で誤解も生じやすく、制度を正しく理解していないと控除の適用漏れや誤申告につながります。特に、扶養控除との混同や、保険金収入などの見落としやすい所得の計上漏れには注意が必要です。制度ごとの対象範囲や計算根拠を正確に把握し、従業員への説明と申告内容の確認を丁寧に行うようにしましょう。
●扶養控除とは異なる
配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者に対する所得控除で、扶養控除とは別の制度として運用されています。配偶者控除・配偶者特別控除は一人の納税者につき一人の配偶者のみが対象となります。
一方、扶養控除は配偶者以外の親族(子・親・兄弟姉妹など)を対象とし、要件を満たす扶養親族であれば人数制限はありません。また、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりませんが、扶養控除にはこのような所得制限はありません。両制度の違いを正確に把握し、申告時の混同を避けることが重要です。
●生命保険や損害保険の満期保険金も所得に含まれる
配偶者控除や配偶者特別控除においては、パートやアルバイトなどの給与所得だけでなく、公的年金や保険の満期返戻金、一時所得なども「配偶者の合計所得金額」に含まれます。特に保険金の返戻金は見落としやすい所得項目です。配偶者の勤務シフトの調整だけでなく、保険の満期予定や年金所得なども確認して年間の所得見積もりを行い、控除の適用可否を慎重に判断する必要があります。
●配偶者に税金が課せられる場合もある
2025年の税制改正により、配偶者の給与収入が160万円以下であれば所得税が非課税となりました。一方で、この基準を超えると配偶者自身に所得税の納税義務が発生するため、納税者に配偶者特別控除があっても、家計として見ると別に税負担が生じることになります。
納税者本人の税負担が配偶者特別控除によって軽減される一方で、配偶者側には新たな課税が発生する可能性がある点には注意が必要です。担当者は、従業員から相談を受けた際に世帯全体の税負担の視点からアドバイスできるよう、制度の相互関係を整理しておくことが求められます。
●配偶者特別控除は産休・育休中でも申告できる
産休・育休によって配偶者の収入が減少したことで所得要件を満たす場合は、配偶者特別控除の申告が可能です。産休・育休中に支給される育児休業給付金や出産手当金は非課税所得のため、配偶者の合計所得金額には含まれません。従業員に対し、年末調整時に申告の可能性があることを案内し、該当の収入見積額を確認するよう促しましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除の実務でよくある質問
配偶者控除や配偶者特別控除については、年末調整や確定申告の現場で多くの疑問が寄せられます。特に、申請漏れや記載ミスの対応、年収による適用可否など、実務上の判断が求められる場面も少なくありません。ここでは、担当者が従業員からよく尋ねられる代表的な質問をピックアップし、簡潔にポイントを整理しています。正しい対応を把握し、実務に役立てましょう。
- 控除の申請を忘れていた場合はどうすればよい?
-
年末調整で申請を忘れた場合は、翌年1月31日までであれば訂正が可能です。さらに、この期限後でも確定申告で訂正対応ができ、5年以内であれば還付申告が可能です。所定の申告書を税務署に提出すれば、控除を反映した還付金を受け取ることができます。
- 記載内容に誤りがあった場合はどうすればよい?
-
申告書の記載ミスに気づいた場合、翌年1月31日かつ源泉徴収票発行前であれば、二重線と訂正印で該当箇所を示すことで修正できます。源泉徴収票発行後は確定申告での対応となり、期限内であれば訂正した申告書を再提出、期限後は「修正申告」または「更正の請求」で手続きします。
- 夫と妻が互いに配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできない?
-
夫婦が互いに配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。制度上、控除を受けられるのはどちらか一方のみで、双方が同時に適用を受けることは認められていません。
- 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける妻(もしくは夫)が、パートで働いても損をしない年収は?
-
2025年以降、税負担が増えにくい年収の上限が大幅に引き上げられました。配偶者控除の対象となるには年収123万円以下、配偶者特別控除の満額適用を受けるには年収160万円です。年収に応じた税負担の違いを確認し、就業計画を立てる際の参考としてください。
- 配偶者控除・配偶者特別控除から外れる夫(もしくは妻)の年収は?
-
配偶者の年収が201万6,000円を超えると、配偶者特別控除の対象外になります。また、納税者本人の年収が1,195万円を超える場合も控除は適用されません。申告時の確認漏れを防ぐため、両者の収入状況を事前に把握しておくことが重要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の年末調整を支えるクラウドサービスの活用
これまで解説してきた配偶者控除・配偶者特別控除の制度を理解することはもちろん重要ですが、実際の年末調整業務では、申告書の配付・回収・記載内容の確認といった実務作業が発生します。制度の複雑さや改正点の多さから、毎年の対応に手間取る担当者も少なくありません。
年末調整の業務負担を軽減するには、作業工程の効率化が欠かせません。ここでは、配偶者控除・配偶者特別控除の実務対応と業務効率化の観点から、年末調整クラウドサービスの活用方法を紹介します。
●配偶者控除・配偶者特別控除の申告業務をクラウドで効率化・省力化
複雑な年末調整業務に対応するには、作業プロセス全体のデジタル化が効果的です。特に申告書の配付・回収や記載内容の確認、給与システムへの転記といった業務は、手作業で行うと記入ミスや漏れが生じやすく、担当者の負担も大きくなります。年に一度しかないため、手続き方法や書類作成に不慣れな従業員も多く、これがミスの原因になることも少なくありません。
「奉行Edge 年末調整申告書クラウド」は、こうした年末調整の一連の流れをクラウド上で完結できるサービスで、配偶者控除・配偶者特別控除に関する記載内容もオンラインで収集・確認できます。申告内容の自動チェック・自動計算や入力補助機能により、作業時間を従来比8割削減できるため、業務負担を大幅に軽減できます。
担当者は、制度改正による新たな「年収の壁」への対応や、従業員からの問合せ対応も求められるため、こうしたクラウドサービスの活用が、正確かつスピーディな年末調整の実現に直結します。人的ミスを防ぎ、全体の申告業務を効率よく進めるためにも、サービス導入による業務改善が今後のカギとなるでしょう。
関連リンク
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!