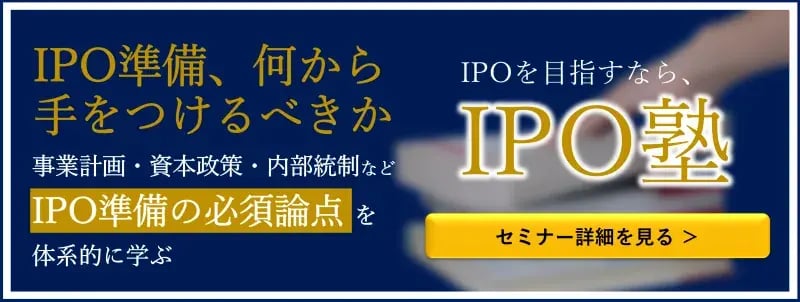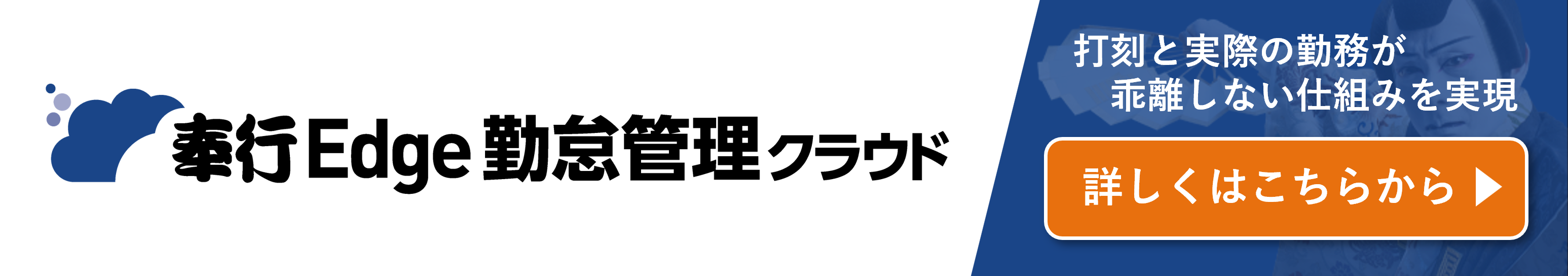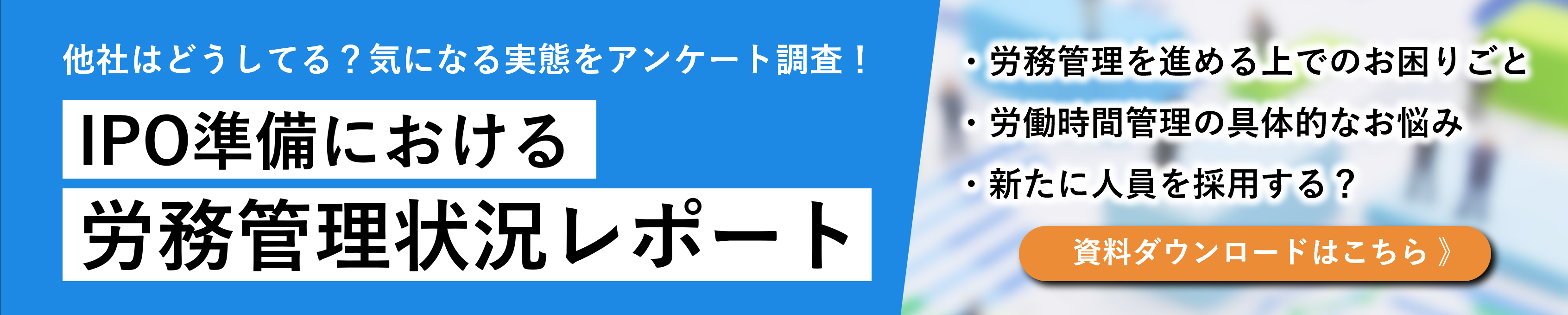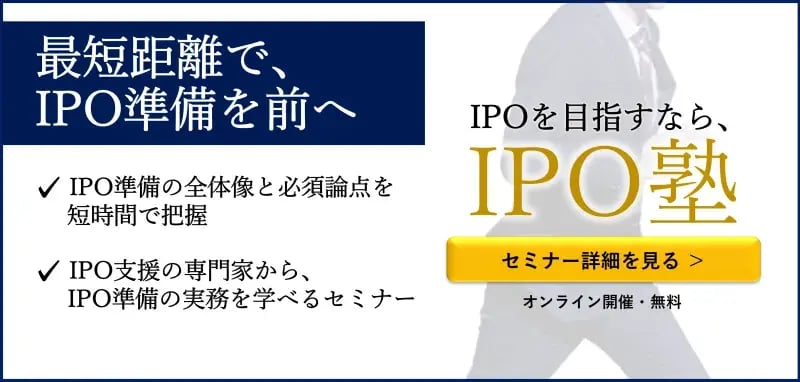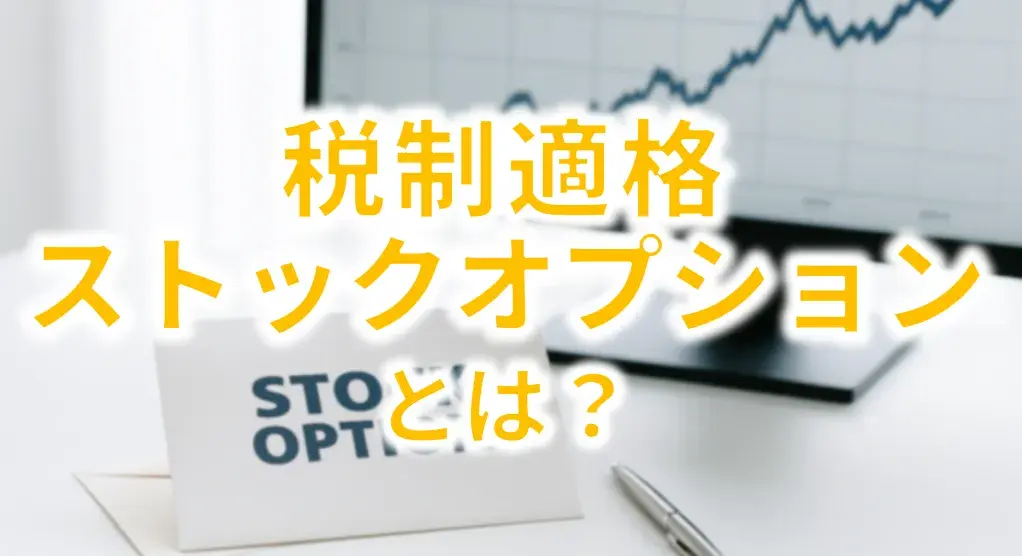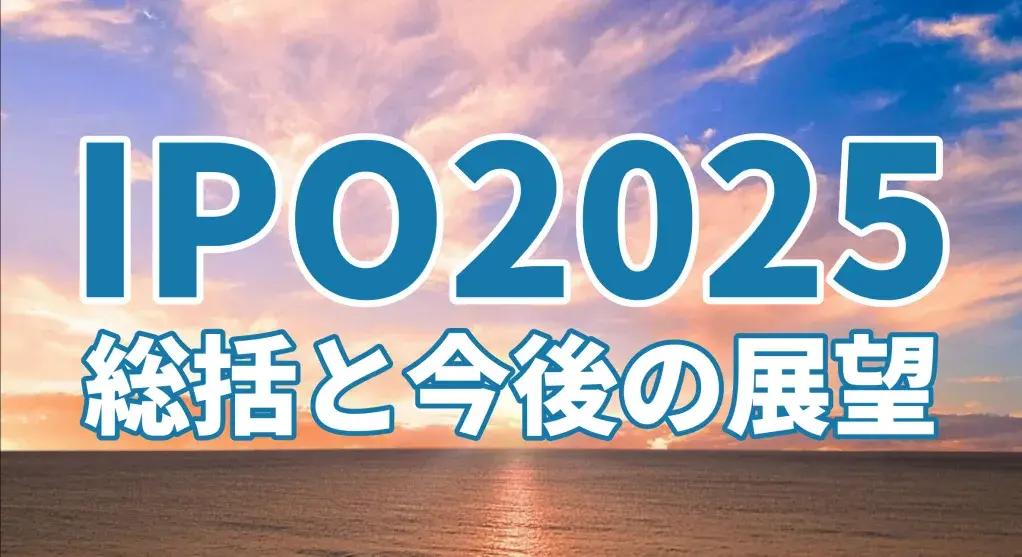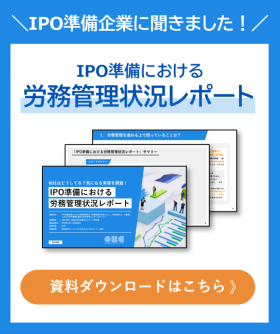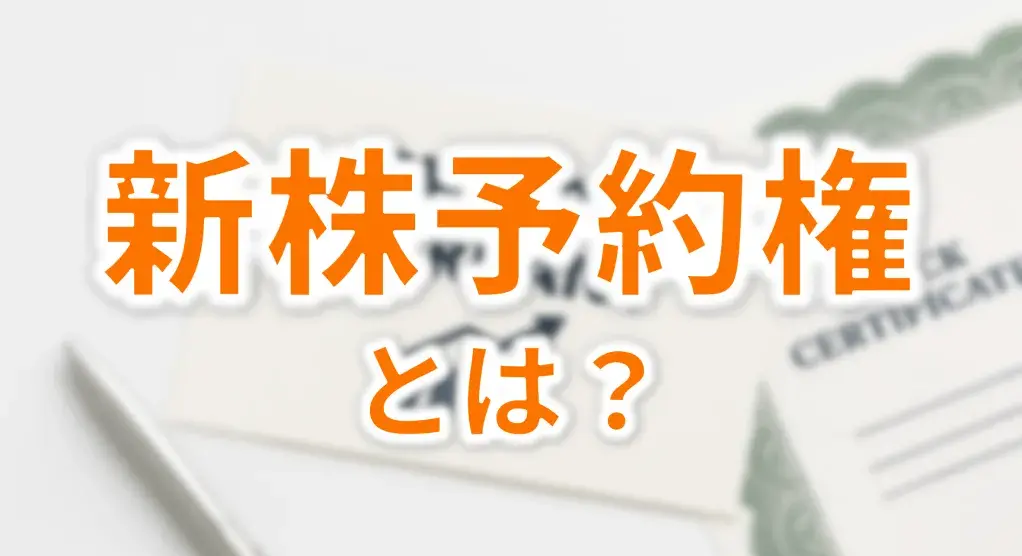

労働時間管理とは、労働者が「どれだけ・いつ・どのように」働いたかを、企業が正確に把握し、法令に基づいて適切に管理することを指します。厚生労働省のガイドラインをふまえた企業が講ずべき対応策や、IPO審査で問われる労働時間管理のポイントを解説します。

- ■執筆:アイ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士
土屋 信彦氏 - 社会保険労務士として35年以上のキャリアを有し、得意分野はIPOやM&A及びリスク対応にかかわる労務監査や就業規則整備。証券会社、税理士会、宅建業協会、異業種交流会等でのセミナー多数。埼玉県社会保険労務士会理事、社会保険労務士会川口支部副支部長等を歴任。名南経営LCG会員。上場実務研究士業会会員。
- アイ社会保険労務士法人 ホームページ
目次
1.労働時間管理とは?実施主体の捉え方
労働時間管理とは、労働者が「どれだけ・いつ・どのように」働いたかを、企業が正確に把握し、法令に基づいて適切に管理することを指します。これは単なる勤怠データの収集にとどまらず、業務命令の有無や健康配慮、安全配慮義務といった観点も含めて、広く“働いた時間”をどう認識し、処遇に反映させるかという企業の重要な責任でもあります。
では、労働時間を管理する責務は誰が負っているのでしょうか?
実際に働く労働者側でしょうか?それとも企業側でしょうか?
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)によると、「労働基準法(以下、労基法)においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。」として、企業側に責任があることを明確にしています。
また、労働安全衛生法(以下、安衛法)では、「事業者は、医師による面接指導を適切に行うために、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」と定められています(安衛法第66条の8の3)。これは長時間労働者の健康リスクを未然に防ぐための規定であり、企業には健康管理の観点からも労働時間の把握が求められていることを意味します。
整理すると、労基法では「適正な賃金の支払い確保」を目的として、安衛法では「健康を管理する面接指導の実施」のため、両法で労働時間管理を“企業の責務”としているのです。
2.厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の概要
このガイドラインは、未払賃金や過重労働が社会問題化する中、2017年1月に厚生労働省によって策定されたものです。ガイドラインそのものは法的拘束力を持つものではありませんが、このガイドラインで記載された労働時間の適正把握義務については、そのまま安衛法に組み込まれ、2019年4月に施行された働き方改革関連法の中核となりました。つまり、労働時間の適正把握義務は法令として格上げされ、法的拘束力を持つことになったのです。
それにより労働基準監督署では、労働時間の適正把握義務を明確な根拠として取り締まり、違反した場合は「是正勧告書」を交付して指導し、結果の報告も求めるという厳しい対応ができるようになりました。指導について、具体的な手法や運用はガイドラインに記載された内容に基づいて行うため、ガイドライン自体も、労働時間管理において非常に重要な位置づけとなっています。
以下では、ガイドラインに示されている「労働時間」の定義と適用範囲を引用して解説します。
参考)厚生労働省PDF「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
2-1.労働時間の定義
労基法第32条では、労働者に対して、休憩時間を除き1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないとされています。ここでいう「労働時間」とは、単に就業規則や雇用契約書に記載された時間だけではなく、実際に労働者が使用者の指揮命令のもとで働いていると客観的に評価される時間すべてを含むものと解されています。
厚生労働省のガイドラインでも同様に、労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指すとされており、企業の明示または黙示の指示により業務に従事している時間は、すべて労働時間に該当します。
たとえば、ガイドラインでは、次のような時間は、労働時間として扱わなければならないとしています。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
→着用が義務づけられている制服への着替えや、清掃当番など、業務の一環として行われる作業が該当します。
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
→運送業や建設業などで、荷積み・荷下ろし等の、いわゆる手待ち時間が該当します。
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
→就業時間外でも、企業命令で受講する研修やe-ラーニングが該当します。
このように、「使用者の指示」に基づいて行動している時間や「業務上義務付けられている」活動については、原則として労働時間にあたる可能性が高いと判断すべきでしょう。
2-2.適用範囲(労働時間を把握すべき義務者と対象者)
ガイドラインでは、農業・畜産業・養蚕業・水産業等を除く、労基法の労働時間に関する規定が適用されるすべての企業に対して、労働時間を適正に把握する義務があるとしています。対象となる労働者は、基本的に従業員全員ですが、労基法上の労働時間や休憩、休日労働の適用外とされている「管理監督者」や秘書業務などの「機密事務取扱者」、裁量労働と呼ばれる「みなし労働」の対象者は除きます。
ただし、これらの者も、企業にとっての「労働者」であることに変わりありません。そのためガイドラインには、これらの労働者についても健康確保の観点から適正な労働時間管理を行う責務があることが明記されています。また、同様の観点から、2019年の働き方改革関連法に基づく安衛法解釈通達(改正H31年3月29日付基発 0329第2号)においても、企業に対して管理監督者やみなし労働の対象者の労働時間を把握するよう明記されています。
3.企業が講ずべき対応策
ガイドラインでは、企業が労働時間の適正な把握のために実施すべき具体的な方法について、次のように記載されています。
その1 始業・終業時刻の確認・記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
- (ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
- (イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
その3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。
出典:厚生労働省 PDF「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
- (ア) 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
- (イ) 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
- (ウ) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。- (エ) 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。- (オ) 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。
上記のうち、日ごとの始業・終業時刻の記録は当然のこととして、「客観的記録」と「自主申告による記録」の2つの方法を整理すると、次のようになります。
| 客観的記録 | 自主申告による記録 |
|---|---|
| ・使用者の現認による記録 | ・日報に本人が記載 |
| ・タイムカードによる打刻 | ・エクセル等に自ら時間を入力 |
| ・ICカードによる入退室記録 | |
| ・クラウド勤怠システムによる打刻 | |
| ・PCのログ記録 |
この「事業者が講ずべき措置」は、模範的な対応例と言えます。しかし、現実的にはすべてを完全に実行することは難しい場合もあります。小規模な企業であれば、使用者が直接確認する方法(現認)も可能ですが、企業規模が大きくなるほど現実的には困難になります。
実際の企業対応としては、自己申告制による管理は例外的な措置と捉え、可能な限り客観的な記録に基づく管理を行うことがよいでしょう。
昨今は管理部門のIT化が進んでおり、クラウド勤怠システムを導入することが推奨されます。例えば、奉行Edge 勤怠管理クラウドのように、勤怠データを給与計算システムや人事労務管理システム、会計システムなどと自動連携できる仕組みを導入すれば、企業全体のDX化や業務効率化にもつながるでしょう。
4.IPO審査で問われる労働時間管理のポイント
IPO審査では、労働時間管理に対するチェックは一般的な行政指導よりも一段と厳しく行われます。IPOを目指すなら、労働時間管理を単なる勤怠管理にとどめず、コンプライアンス体制の根幹として捉えることが重要です。
ここでは、IPO審査において特に注目される労働時間管理のポイントを整理します。
4-1.乖離チェック
監督署における労働時間管理の行政指導では、「客観的記録」に基づく勤怠管理を基本としています。しかし、IPO審査ではさらに高いレベルでの労働時間管理を要請している傾向があります。
具体的には、タイムカードやクラウド勤怠システムによる打刻であっても、その記録が間違いなく真正であることを企業が確認をしているかが重視されます。例えば、「打刻後に業務を行っていないか」「一定時間に打刻を要請されたのちに業務命令がされていないか」などをPCのログ記録等で確認し、「乖離チェック」を行っているかを確認されることがあります。概ね30分以上の乖離があれば、その時間が業務か私的な滞在かを明確にしなければなりません。
業務でない、つまり、私的な滞在ならば、「自己研鑽や資格取得のための勉強」や「通勤混雑緩和のため早出入室し新聞購読」のように、業務でない事実を記録として残す必要があります。逆に、打刻後に緊急業務を行った場合などは、打刻記録の補正が必要です。
ガイドラインが求める自主申告方法の乖離チェックは、IPO審査においても必須と考えてよいでしょう。
4-2.社内ルール
就業規則に「上司の承認を得ずに行った時間外の業務は労働時間とみなさない」と規定している企業は少なくありません。
ガイドラインでも「就業規則等の定めのいかんによらず」と記されているように、実際に業務を行った時間は、承認の有無に関わらず労働時間に該当します。上司の時間外労働の承認制そのものは、企業のルールとして有効であり、そのルールに違反した従業員は厳重注意や懲戒処分などの対応も必要です。しかし、実際に業務を行ったことを労働時間と認めない運用は法令違反であり許されません。
労働時間の把握義務は「使用者(企業)」にある以上、これを軽視することは未払賃金リスクを招き、IPO準備にも影響を及ぼす、極めて危険なことであると強く認識しておかなければなりません。
4-3.給与計算への連携
労働時間管理では、「1分単位」で労働時間を把握し、それを賃金に反映させることが最も重要です。こうした厳格な労働時間管理ができなければ、IPO審査はクリアできないといっても過言ではありません。
就業時間外のメールチェック、就業時間外の取引先対応など、勤怠記録に表れにくく企業が認知できないような業務は、社員に申告を促すことも重要です。こうした対応を怠ると、IPO前に退職した労働者から「勤怠記録以外でも業務を行っていた」と未払残業代を請求されるリスクもあります。
5.最後に
IPO審査で労働時間管理について厳しくなった背景には、未払残業請求による簿外債務リスクがあります。
IPO審査では、決算書に現れない簿外債務を最も嫌う傾向があります。1人の未払賃金が仮に10万円であったとしても、100人規模であれば1,000万円単位の簿外債務に膨らむ可能性があります。さらに労基法では、未払賃金の請求権は3年間有効とされているため、たとえば退職した従業員から過去にさかのぼって請求された結果、想定以上の簿外債務を負う可能性もあるからです。
厚生労働省の発表によると、令和6年の監督指導による賃金不払残業の是正結果は次のようになっています。これによると、令和6年中に支払われた未払分のデータは、対象件数21,495件、対象労働者数181,177人、合計162億円にものぼります。
| (1) | 対象件数 | 21,495件 |
| (2) | 対象労働者数 | 181,177人 |
| (3) | 支払われた割増賃金合計額 | 162億732万円 |
参考)厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)」
このように、実際の是正額は企業にとって決して小さな負担ではありません。IPOを目指す以上は、こうした潜在的な簿外債務を抱えないよう、日頃から正確な労働時間管理を徹底することが不可欠です。
労働時間の打刻は労働者が行うものでも、その打刻が正しいか否かの確認・検証は企業が行う義務であることを、よくよく肝に銘じておきましょう。
IPO Forum ネットワークとは
IPOを目指す経営者や企業をワンストップでサポートする、IPOの専門家によるネットワーク組織。
2014年発足。 事業計画書作成支援、内部統制構築支援などの実務サポートのほか、IPOの審査トレンドを解説する「IPO Forum」を半期に1度開催し、資本政策、労務管理など、IPOに必須の論点を解説する「IPO塾」を年間を通して開催している。メンバーによるコラムも定評がある。
【IPO Forumネットワークメンバー】
宝印刷株式会社 / 株式会社タスク /あいわ税理士法人 / TMI総合法律事務所 /アイ社会保険労務士法人 /株式会社オロ / イシン株式会社 /株式会社サーキュレーション /株式会社プロネット /株式会社オービックビジネスコンサルタント

- 著書「この1冊ですべてがわかる 経営者のためのIPOバイブル 第2版」
(中央経済社) - 監査法人内研修でも活用される、プロが認めたIPO指南書。
株式公開を行うために必要となる前提知識・資本政策・人員体制・IPO準備で絶対にやってはいけないことまで、Q&Aで優しく解説。
(ビジネス専門書オンライン)
関連コラム
IPO Compassメルマガ登録はこちらから!