

「決算」と聞くと、一年に一度行う「年次決算」を連想される方が多いかもしれません。その年次決算と同様に重要なのが「月次決算」です。
中小企業において、すでに月次決算を実施している企業は少なくありません。しかし一方で、「毎月の決算業務は手間がかかるだけで面倒」という経営者や担当者の声も聞かれます。
そもそも、月次決算は何のために行い、何に活かせるのでしょうか? どうすれば「面倒」なく業務を進められるでしょうか?
今回は、月次決算を行うメリットと実務の進め方についてご紹介します。
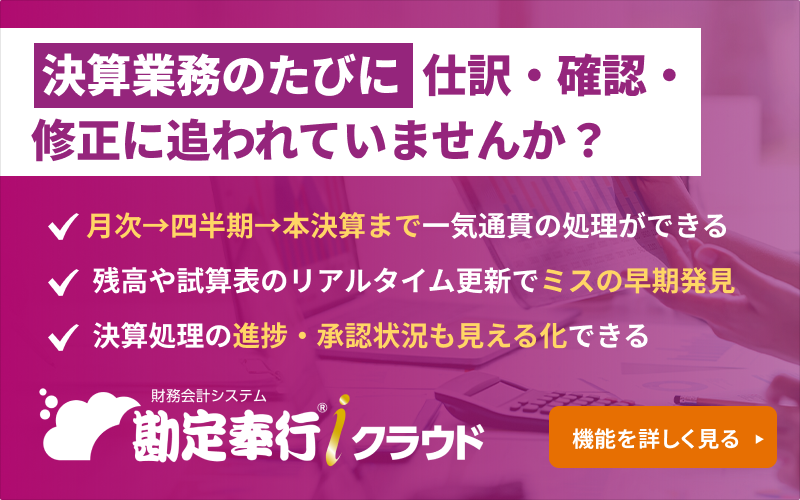
目次
月次決算がもたらすメリットとは
月次決算とは、簡単に言うと「1ヶ月ごとに行う決算業務」です。毎月会計を締めた時点で、年次決算とほぼ同じ会計処理を行います。そう聞くと「業務負担が増えるのでは」と重荷に感じるかもしれません。月次決算には年次決算のように法的義務はありませんので、取り組むかどうかは企業の自由です。
しかし、月次決算を行うと、「業務面」「経営面」で以下のようなメリットを得ることができます。
●年次決算の負担を軽減できる
例えば、仮払金・仮受金といった仮勘定の正確な内容は、何か月も遡って突き止めるのは難しいものです。年次決算で行おうとすると、その作業だけで相当な時間をかけることになるでしょう。月次できちんと処理をしておけば、このような年次決算での業務負担を大きく減らすことができるのです。
また月次決算業務は、年次決算よりもさらに短期間で人手を集中させるように見えます。しかし、月次決算を行えば、会計処理の誤りを早期に発見でき、仕訳において高い精度を維持することができます。
「1年に1度の年次決算業務の一部を毎月に分散する」と考えれば、月次決算は経理担当者の業務効率化に大きく貢献すると言えるでしょう。
●事業戦略を早期に検討できる
月次決算の結果は、節税対策や予算修正などの対策にも活かせます。例えば、月次決算を行うと、年次決算の着地見込も事前に高精度で算出できるため、利益が大きい場合には節税対策を実施する・・・といったことが可能になります。また、予算と実績の差異を把握し比較分析することで、早期に予算修正を行うことができます。資金繰り状況もタイムリーに把握できるので、融資などを考慮した資金計画も立てやすくなります。
特に、経営層にとっては、月次決算の結果を基に、自社の業績に合わせて経営方針を的確かつ迅速に修正できるようになります。つねに事業計画を見直せるので、事業の成長を加速させることも容易になります。
●金融機関から円滑に融資を受けられる
金融機関は、融資希望の企業を調査した上で融資の可否を判断します。実際には融資が可能であっても、直近の業績がわからないと、融資の判断が下るまでの調査が長期化することもあります。月次決算の報告書は、金融機関が融資の判断をするための材料になるので、融資を求める際に提出すれば融資の判断スピードが早められるでしょう。
また、月次決算を実施しているという事実自体が、金融機関からの心証をよくするため、「融資を受けやすくなる」という効果もあります。
月次決算業務の流れ・スケジュール
月次決算業務で大切なことは、「正確性」と「対応スピード」です。
「作業手順はほぼ年次決算と同じ」とはいえ、通常1ヶ月以上かかる年次決算と同じフローで対応していては、到底間に合いません。1日でも早く月次決算を正確に完了させるためには、期限を決めてスケジュールを組み、段取りよく進める必要があります。
月次決算業務には、大きく「決算整理」「決算書の作成」「事業報告」の業務があります。
月次決算のメリットを活かすという意味では、遅くとも中旬までには決算報告を済ませておく必要があります。企業規模によっても異なりますが、月次の締日から5営業日までには結果の算出を完了させることが理想的でしょう。
<月次決算業務の流れ>
- 請求書などの締日
- 請求書等の提出・経費精算
(締日より2〜3日内) - 決算整理
- 決算書作成
(5〜8営業日後) - 月次会議報告
(10営業日後)
① 決算整理
決算整理では、主に以下の作業を行います。
● 現金・預金の残高確認
現金・預金勘定の帳簿残高に差異がないよう調整します。現金は金庫にある金額を数え、預金は記帳して確認し、もし差異や齟齬があれば原因を追求し、修正していきます。
● 月次の棚卸し確定
月末時の在庫金額を確定します。ただし月次決算の場合、「棚卸資産管理手続き」の整備を条件に、実地棚卸しを省略することができます。
● 仮勘定の整理
仮払金や仮受金などを、適正な科目に振り替えます。
● 経過勘定の計上
未払費用や前払い費用を計上します。月次決算では、対象項目や計上基準をあらかじめ設定しておくことで、迅速に計上を完了させることができます。
● 減価償却費、引当金、納税充当金等の計上
年間費用を見積もり、1年におけるそれぞれの12分の1で割った金額を計上します。
② 月次決算書(試算表)の作成
業績の推移を把握するため、経営陣が役立つと判断した資料を作成します。年次決算と異なり、必須となる書類はありませんが、概ね以下のようなものを準備するとよいでしょう。
- 損益計算書
- 賃借対照表
- 資金繰り表
- その他資料・・・予算実績対比表、前年同月対比表、部門別損益計算書、借入金一覧表、売上高推移表(品目別、得意先別など)、受注残高表(品目別、得意先別など)、経費推移表、売掛金残高表、買掛金残高表、在庫一覧表など
全社資料の他に、必要に応じて各部門別や事業所別でも作成しておくと、部門単位での業績を把握できるので便利です。
③ 月次事業報告
月次決算書をまとめたら速やかに経営層に報告します。
遅滞なく月次決算を行うための方法とは
月次決算が遅れるということは、「経営判断が遅れる」ことに他なりません。
しかし、準備物の収集やスケジュールがタイトなため、業務が滞ることもしばしばあります。
ここでは、業務が滞りやすい要因と、月次決算の早期化対策について整理してみましょう。
■ 業務遅延を起こす要因
月次決算業務が滞る主な要因には、次のようなものがあります。
● 各部署での処理業務が遅れる
「仕入先から請求書が届かず仕入計上ができない」「営業担当部署からの売上・仕入計上報告が遅れる」「在庫のチェックに時間がかかる」「証憑類の承認が遅れる」など、各部署で起こる問題はよく聞かれるものです。
各部署で処理業務が遅れると、その後をまとめる経理部門での月次処理に大きく影響します。
また、月次決算では、正社員はもちろん、部門ごとに管理しているアルバイトやパートの給与や残業代も反映させなければなりません。各部署で彼らの労働時間の集計が遅れることも、月次決算業務に影響することになります。
● 会計処理、確認作業に時間がかかる
例えば、証憑のチェックや整理など会計業務のうち手作業で行う作業が多いと、その処理に多くの時間と労力がかかってしまいます。ただでさえ、月度締日の経理部門には大量の請求書や経費精算された証憑類が届きます。普段から伝票発生時に処理せず一度にまとめて経理処理していると、月次決算の時期に業務が集中して、さらに大きな負担になりかねません。
また、請求書と納品書の突き合わせ作業や入力内容の確認作業なども、問題となりやすい点です。ミスがないように複数の従業員でチェックするとなると、多くの労力や時間がかかってしまうことにもなります。
■ 業務早期化に向けた対策
業務の遅延を防ぐためには、次のような対策を行い、月次決算の早期化を図ることが重要です。
● 社内・社外へ締切日を徹底する
月次決算の遅延を防ぐには、請求書や納品書、経費精算の伝票を期限通りに提出してもらうことが不可欠です。締切日を社内へ事前アナウンスしておき、早めに証憑類が経理部門に集まるよう徹底しましょう。また、社外の取引先に対しても締切日の厳守について協力を仰ぐことも有用です。
● 月次決算スケジュールを社内で共有する
決算において、各部門・部署との連携は欠かせません。社内で月次決算の目的とスケジュールを共有することも意識しておきたいポイントです。月次決算を自分事として理解し取り組んでもらうことで、よりスムーズなプロセスを組みやすく、進捗管理もしやすくなります。
● クラウド型システムを活用する
実は、各部門で行われる経費精算など、日次業務を改善することでも月次決算の早期化を図ることができます。
例えば、会計システムをクラウド化すると、金融機関の入出金データを取り込んで自動仕訳ができるので、預金残高の確認・記帳が簡単になります。最近では、領収書などの証憑を取り込み、自動仕訳・起票する機能を備えたサービスもあります。
「いつでもどこからでもアクセスできる」というクラウドのメリットを活かせば、税理士とデータを共有し、仕訳処理で分からないことなど日常の疑問をすぐに確認、解決することも可能になります。また、経営者もリアルタイムに必要な情報を見られるので、レポートを待たずとも短時間で情報共有できるようにもなるのです。
おわりに
初めて月次決算を行う場合は、業務の流れに慣れるまでは大変かもしれません。しかし、一度行えば、業績の現状把握やスピーディーな経営判断など多くのメリットを得られます。そしてそれは、今後の企業発展に大きく役立つものになります。
各部署のコミュニケーションをより密にし、情報共有や必要書類収集のスピードアップを図りながら、経営の健全・安定化に繋がる“意味のある月次決算”に取り組んでみてください。
月次決算に関するよくあるご質問
- 月次決算とは?
- 月次決算とは、簡単に言うと「1ヶ月ごとに行う決算業務」です。毎月会計を締めた時点で、年次決算とほぼ同じ会計処理を行います。そう聞くと「業務負担が増えるのでは」と重荷に感じるかもしれません。月次決算には年次決算のように法的義務はありませんので、取り組むかどうかは企業の自由です。
- 月次決算業務の流れ・スケジュールは?
- 月次決算業務で大切なことは、「正確性」と「対応スピード」です。
「作業手順はほぼ年次決算と同じ」とはいえ、通常1ヶ月以上かかる年次決算と同じフローで対応していては、到底間に合いません。1日でも早く月次決算を正確に完了させるためには、期限を決めてスケジュールを組み、段取りよく進める必要があります。
月次決算業務には、大きく「決算整理」「決算書の作成」「事業報告」の業務があります。
月次決算のメリットを活かすという意味では、遅くとも中旬までには決算報告を済ませておく必要があります。企業規模によっても異なりますが、月次の締日から5営業日までには結果の算出を完了させることが理想的でしょう。
こちらの記事もおすすめ
- 会計システム選びで悩んだら?検討時に押さえておくべき6つのポイントとは
- もう迷わない!失敗しない会計ソフトの選び方|業務の悩みを解決する「クラウド」の実力とは
- 決算期を乗り切れ!中小企業が年次決算で押さえておくべき業務の流れ
関連コンテンツ
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

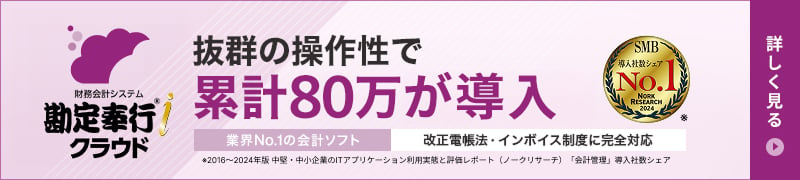
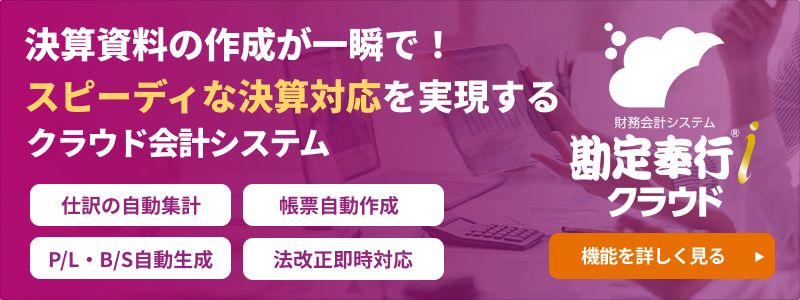
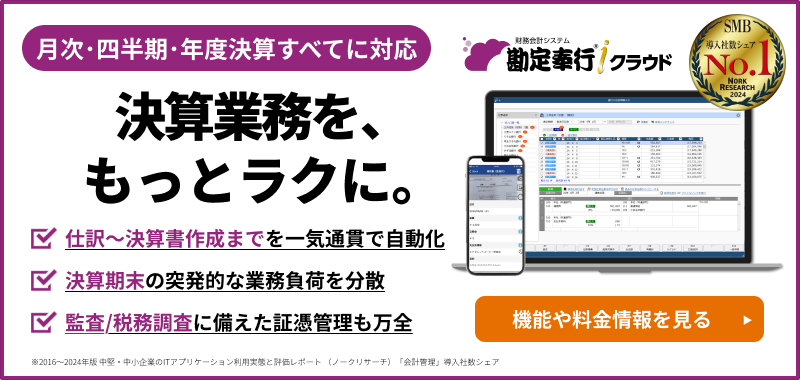

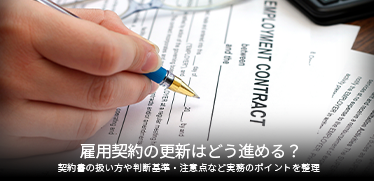
![[雇用保険料の計算どうする?]実務で迷いやすいポイントと正確性を保つ方法とは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post480_thumb.png)
