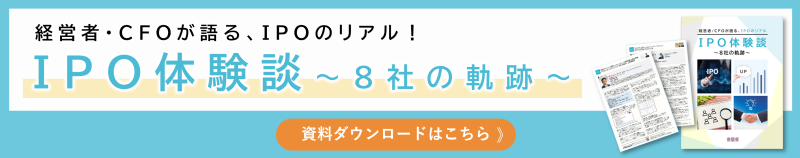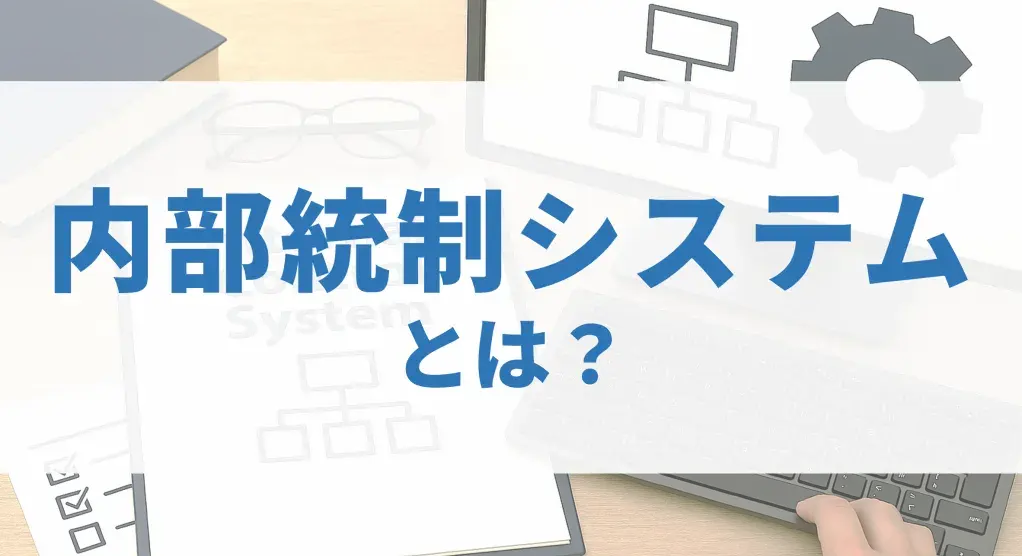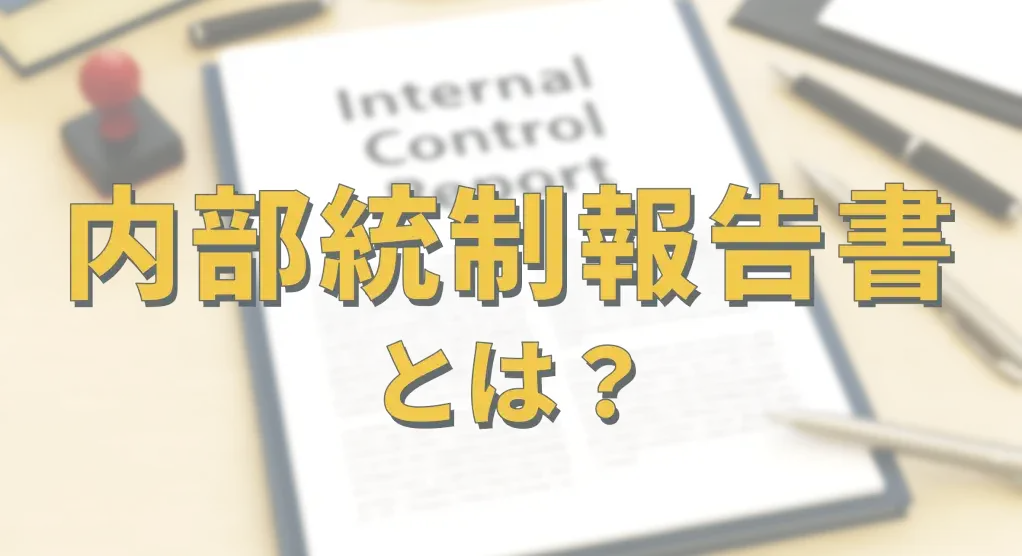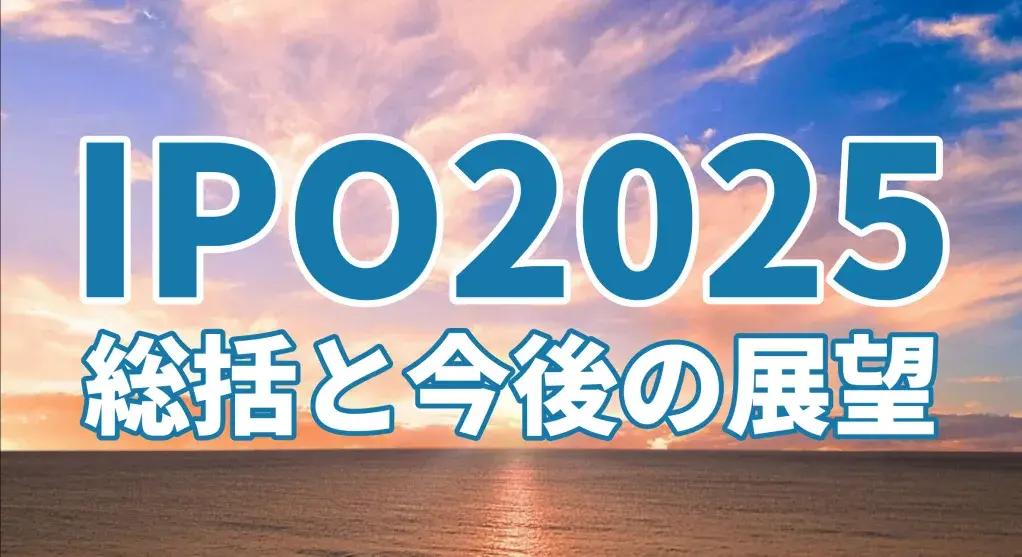

株式上場とは何か?上場する市場にはどのような種類があるのか?これから上場を検討する企業が知っておきたいメリット・デメリットと昨今のトレンドを解説します。

- ■執筆:IPO Compass編集部
- スムーズなIPOに近づくためのコラム・セミナーを企画しています。
目次
- 1.株式上場(新規株式公開・IPO)とは何か?
- 1-1.上場・非上場の違い
- 1-2.上場する市場の種類は?
- (1)東京証券取引所
- (2)名古屋証券取引所
- (3)その他(福岡証券取引所・札幌証券取引所)
- 2.上場のメリット
- (1)資金調達方法の多様化と資金調達力の向上
- (2)知名度・信用力の向上
- (3)人材確保の優位性、従業員の士気向上
- (4)管理体制の強化・充実
- (5)創業者利潤の実現
- 3.上場のデメリット
- (1)会社情報の開示義務とその体制の確立
- (2)敵対的買収等、株式買占めへの対応
- (3)株主対策(コミュニケーション)
- (4)上場維持コストの発生
- 4.変わる、上場のメリット・デメリット
- (1)“資金調達”手段は上場だけではない、VC・CVCによる投資やM&Aの時代に
- (2)“敵対的(同意なき)TOB”増加
- (3)求められる投資家コミュニケーション
- 5.株式上場に関するよくあるご質問
1.株式上場(新規株式公開・IPO)とは何か?
株式上場、つまり新規株式公開(IPO:Initial Public Offering)とは、株主が同族あるいは特定の少数者のみに限られている状態から、株式を証券市場に流通させることによって、広く一般の投資家に資本参加を求めることをいいます(所有と経営の分離の明確化)。上場により会社の株式は多数の投資家に保有・取引され、また金融商品取引法の規制のもとに、株式の投資判断のための情報開示が行われることとなります。
【関連コラム】 IPO(新規株式公開、株式上場)とは?上場の意味・目的・経営者の心構えを解説
1-1.上場・非上場の違い
上場と非上場の違いは、株式を証券取引所に公開しているかどうかです。
上場することで一般投資家に株式が公開され、誰でも株式を売買できます。一方、非上場の場合は株式を公開していないため、証券取引所において株式の売買はできません。非上場企業における公開されていない株式は「未公開株」、「非上場株式」と呼ばれます。
未公開株を売買する場合には、その企業の未公開株を保有する、経営陣などの株主と直接交渉して譲受する方法や、M&Aによる株式譲渡、ストックオプションによる株式付与などの方法が一般的です。
上場企業と比べて株式の売買が容易ではなく、一般投資家などが経営に参加しづらい分、株式買占めによる買収リスクが低いことや、経営の自由度が高いことはメリットと言えます。反対に、証券取引所で株式の売買ができないことで資金調達がしづらい点はデメリットと言えます。
1-2.上場する市場の種類は?
上場市場は、東京・名古屋・福岡・札幌の全国4か所にあります。各証券取引所には、それぞれに会社の規模やステージに応じた市場区分があります。
東京証券取引所には、日本の上場企業(3,942社、東京プロマーケット含まず、2024年1月17日時点)のうち約98%が上場しています。次に規模の大きい名古屋証券取引所には約7%(他市場との重複上場含む)が上場しています。2つの取引所にある各市場を確認しましょう。
(1)東京証券取引所
東証には、本則(一部、二部)、マザーズ、JASDAQ(スタンダード、グロース)と、いくつかの市場が存在していましたが、2022年4月から新しい市場区分になりました。新市場区分には、それぞれのコンセプトに応じ、時価総額(流動性)やコーポレートガバナンスなどに係る定量的・定性的な基準が設けられています。
| 市場区分 | コンセプト |
|---|---|
| プライム市場 | 多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備える企業向けの市場 |
| スタンダード市場 | 公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備える企業向けの市場 |
| グロース市場 | 高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる企業向けの市場 |
グロース市場に上場できるほど「高い」成長性は説明できず、一方でスタンダード市場に上場できるほどの企業規模がない場合は、これら東証の一般市場ではなく、名証、福証、札証への上場を目指すか、もしくはプロ投資家向け市場(TOKYO PRO Market)を検討することになります。
TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)
より自由度の高い上場基準・開示制度で上場を実現できるプロ投資家向け市場です。2024年1月17日時点での上場企業数は91社で、2023年の新規上場社数は過去最大の32社(前年比11社増)と、ここ数年の間に上場社数を伸ばしています。一般の投資家が売買できないため、資金調達よりも知名度や信用力の向上を目的とした上場がほとんどです。TOKYO PRO Marketへの上場を経由して、東証や名証の一般市場へステップアップする企業も増えていることから、上場先市場の選択先として注目を集めています。
(2)名古屋証券取引所
市場第一部・市場第二部(本則市場)とセントレックス(新興市場)がありましたが、2022年4月より新市場区分に変更されました。本社所在地は名古屋ですが、東海地方以外の企業も数多く上場しています。
| 市場区分 | コンセプト |
|---|---|
| プレミア市場 | 優れた収益基盤・財務状態に基づく高い市場評価を有し、個人投資家をはじめとする多くの投資家の継続的な保有対象となりうる企業向けの市場 |
| メイン市場 | 安定した経営基盤が確立され、一定の事業業績に基づく市場評価を有し、個人投資家をはじめとする多くの投資家の継続的な保有対象となりうる企業向けの市場 |
| ネクスト市場 | 将来のステップアップを見据えた事業計画及び進捗の適時・適切な開示が行われ、一定の市場評価を得ながら成長を目指す企業向けの市場 |
(3)その他(福岡証券取引所・札幌証券取引所)
福岡証券取引所には「本則市場」と「Q-Board」(新興市場)が、札幌証券取引所には「本則市場」と「アンビシャス」(新興市場)があります。2023年6月27日には株式会社GSIが、札幌証券取引所の本則市場へ2000年以来、約23年ぶりとなる単独上場を果たしたことで話題となりました。
上場/売買制度(福岡証券取引所ホームページ)
上場を目指す皆様へ(札幌証券取引所ホームページ)
2.上場のメリット
上場のメリットを会社と株主の観点で確認しましょう。
◇ 会社にとってのメリット
(1)資金調達方法の多様化と資金調達力の向上
証券市場から様々な形での資金調達(時価発行増資・新株予約権付社債の発行等)が可能となり、直接金融の恩恵を受けることができます。その結果、自己資本が充実し財務体質の強化が図られ、成長を加速させるためのベースとなります。
(2)知名度・信用力の向上
実質的に約380万社と言われている日本企業の中の上場企業約3,900社の1社に選ばれることで会社の知名度は高まります。金融機関の信頼性も向上し、資金調達と同等の潜在的なメリットも享受できます。
(3)人材確保の優位性、従業員の士気向上
知名度の向上は営業上のメリットや優秀な人材の確保、従業員の士気向上などにもつながり、企業成長を大きく加速させます。
(4)管理体制の強化・充実
上場準備の過程では、上場会社としてふさわしい内部管理体制を構築することが求められます。その結果、組織が属人的経営から組織的運営に転換され、企業規模拡大にも耐えうる組織基盤が構築されます。
◇ 株主(創業者)にとってのメリット
(5)創業者利潤の実現
経営者は、上場時の株式の売り出しによって投下資本の一部を回収し、創業者利潤を実現することができます。また、株式が証券市場で流通し、公正な株価が形成されることによって、株式の換金性が増大し、株主の財産形成が図られます。
3.上場のデメリット
(1)会社情報の開示義務とその体制の確立
有価証券報告書や四半期報告書の発行義務を負うとともに、決算短信を発表するなど、投資家に対して情報を適時かつ適切に公表する、いわゆる適時開示が必要となります。また、適時開示を行うためには、その体制を確立する必要があります。
(2)敵対的(同意なき)TOB等、株式買占めへの対応
株式市場では、市場で不特定多数の株主が自由に売買できることから、常に買収のリスクにさらされます。経営のっとりを目的とした敵対的(同意なき)TOBへの対策をどのようにしていくか、という点に関しても、上場準備の段階から念頭に入れておく必要があります。
(3)株主対策(コミュニケーション)
上場することによって、不特定多数の株主が存在するようになります。一般株主の多くが興味を持っている配当、株式売却などの経済的利益をどのように維持していくか、必ずしも友好的な株主ばかりとは限らない中で、円滑な株主総会運営などの対策が必要となります。昨今ではアクティビスト(もの言う株主)により、コーポレートガバナンスへの対応が厳しく追及されるケースも増えています。取締役会の機能発揮、ダイバーシティの確保、サステナビリティへの対応等、数年前より格段に検討事項が増えています。
(4)上場維持コストの発生
取引所に支払う年間上場料、監査法人への監査報酬、株主名簿管理人である信託銀行への株式事務代行手数料等、上場後も継続して払う必要があります。また、適時開示体制を確立するためのコストや株主総会運営やIRに関するコストなどもあります。
【関連コラム】 IPO(新規株式公開、株式上場)とは?上場の意味・目的・経営者の心構えを解説
4.変わる、上場のメリット・デメリット
一般的な上場のメリット・デメリットを見てきましたが、昨今ではその定説が変わりつつあります。
(1)“資金調達”手段は上場だけではない、VC・CVCによる投資やM&Aの時代に
上場のメリットとして必ず挙げられる“資金調達”ですが、近年では、VCやCVC(大手企業がオープンイノベーションを見据えて成長性の高いベンチャー企業等へ資金提供するコーポレートベンチャーキャピタル)によるスタートアップ企業への投資が加速しています。また、将来的な上場を目指して上場前に投資ファンドに買収(M&A)される企業も増えています。創業者のファーストイグジットを実現するとともに、経営管理面のサポートなどを得て、上場に向けて成長を加速させる目的です。
2023年は、世界的にスタートアップへの投資環境が厳しい中、日本では世界で唯一のゼロ金利政策が続いたことや、岸田政権の「スタートアップ育成5か年計画」もありVC等の投資意欲は引き続き堅調と言える結果になりました。
資金調達手段が多様化する中、上場だけが選択肢ではありません。自社の技術やサービスを必要としている大手企業との協業や世界の投資家を視野に入れることで新しい可能性が生まれるのです。
(2)“敵対的(同意なき)TOB”増加
2019年以降、敵対的(同意なき)TOBの全体件数・成功件数は急増しています。
事業会社によるTOBは近年高い確率で成功しており、資本業務提携の一形態として確立されつつあります。またアクティビストによるTOBも増加しています。
2023年8月には経済産業省が「企業買収における行動指針」を発表しました。指針では企業買収において尊重するべき3つの原則が明確化されており、真摯な提案に対しては真摯な検討をしなければならず、保身による対抗措置は認められません。
■経済産業省「企業買収における行動指針(案) ―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」, 2023年8月
企業が取るべき最も効果的な対策としては、日ごろから経営陣が企業価値向上施策を実施することや、IRで自社の強み・将来性を市場にPRしていくことで、適正な企業価値を株価に反映させることです。その結果、不適正な価格で敵対的(同意なき)TOBをされるという不測の事態は免れると考えられます。
(3)求められる投資家コミュニケーション
2000年以降の日本市場は、海外機関投資家が最大の投資主体となり、売買状況で圧倒的な割合を占めています。いまや日本市場のプライスリーダーは海外機関投資家と言える状況です。
企業においては、東証からのPBR1倍割れ解消要請やコーポレート・ガバナンスコードにより政策保有株(持ち合い株)の解消が進む一方で、安定株主が減少し、株主構成が盤石ではない状況に置かれているとも言えます。
従来の株主還元策である自社株買いや増配も対策としてはあるものの、その効果が長期にわたり持続するとは言い難い状況です。その場しのぎの株主対策ではなく、多様化する株主とその要求にどのように答えていくかが問われていると言えます。
企業価値向上と株主価値向上を同時に実現するためには、投資家と対話が重要です。
そして対話のためには、IRの充実が欠かせません。従来通りの財務情報の開示だけでなく、サステナビリティのような非財務情報の開示を充実させるなど、ニューノーマルな投資家コミュニケーションを実践することが求められているのです。
5.株式上場に関するよくあるご質問
- 上場するメリットは?
- 一番のメリットは、やはり資金調達でしょう。
証券取引所に株式を公開することで、証券市場から様々な形での資金調達(時価発行増資・新株予約権付社債の発行等)が可能となり、直接金融の恩恵を受けることができます。そのほか、知名度・信用力の向上、人材確保、管理体制強化、創業者利潤の実現なども挙げられます。
- 上場するデメリットは?
- 上場企業として果たすべき開示等の義務が発生すること、上場維持コストがかかること、経営状態やIR次第では株主から厳しい株主提案を受けてしまうこともあります。また買収の恐れもあります。
- なぜ上場しない会社があるのか?
- そもそも日本の99%が非上場企業であり、すべての会社が上場を目指しているわけでもありません。たとえばサントリーやYKKは、誰もが知っている超大手企業ですが、上場していません。上場しない理由としては、自己資金もしくは間接金融で事業資金が賄える、上場するためにコストをかけるよりも事業のために利用したい、株主の意向に左右されずに経営方針を決定したいなどが挙げられます。
上場のメリットを享受する必要がない、もしくはデメリットがメリットを上回ってしまう場合は上場しないという選択もあるでしょう。
関連コラム
IPO Compassメルマガ登録はこちらから!