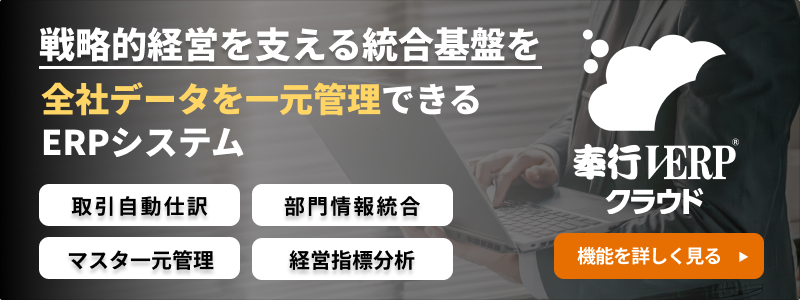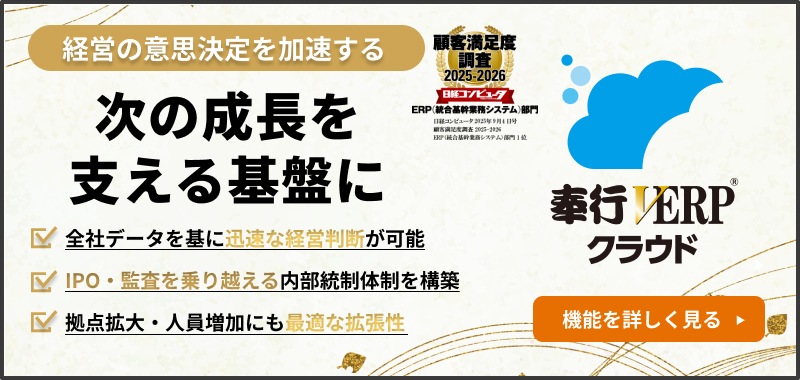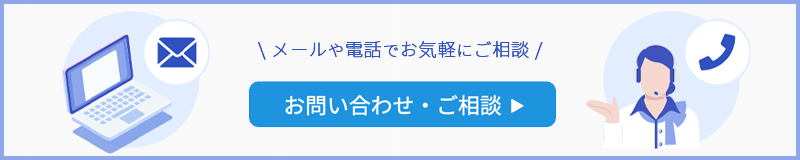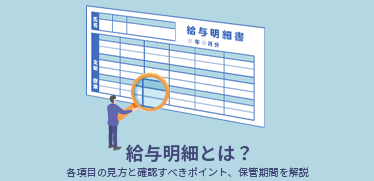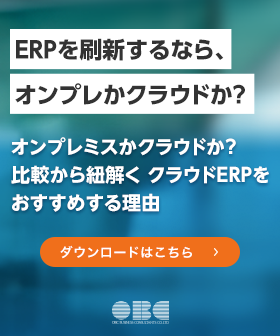企業の業務システムで、今多くの企業が抱えている問題に「システムの老朽化」があります。放置すると、業務の停滞やセキュリティリスクの増加など様々なトラブルが発生し、経済的損失につながる危険性も指摘されています。毎日業務を行う上では問題がないように思えるため、運用に直接関与しない立場ではその兆候を見逃すこともあります。
そこで今回は、システムの老朽化について、業務担当者も押さえておきたい問題点や対処法などを解説します。
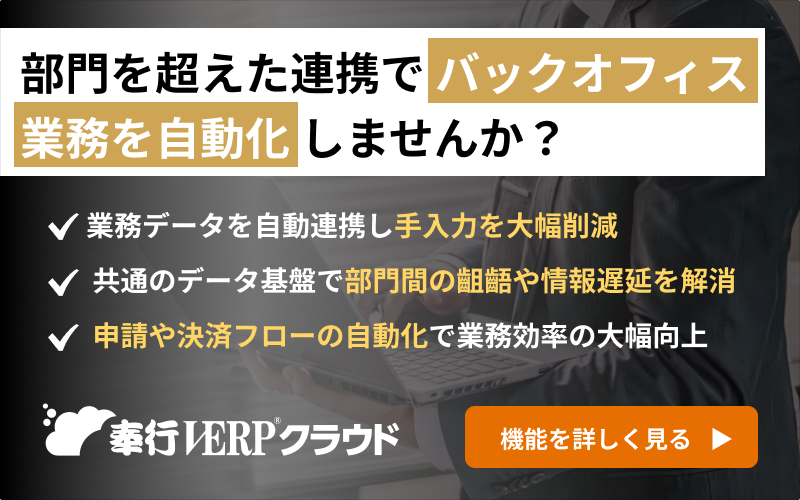
目次
- システムの老朽化はなぜ起こる?
- 企業が直面しやすいシステム老朽化のリスクと課題
- システム老朽化の見極め方・7つのサイン
- システム老朽化問題の解決策|今とるべき選択肢はクラウド移行!
- システム老朽化問題は早めにベンダーに相談を!
システムの老朽化はなぜ起こる?
システムの老朽化とは、使用しているITシステムが時代遅れになり、運用や保守に問題が生じる状態を指します。
毎日の業務で使用するシステムは、トラブルがなければ「今のままで大丈夫」と楽観してしまうケースが多くあります。しかし、オンプレミス型ERPなど長年使用しているシステムでは、過去の技術や仕組みで構築されており、機能を追加しようとしても、最新の技術を組み合わせられないことがあります。
新しい技術を取り入れられない状態は、システムが進化できない=老朽化が進んでいると言えるのです。
経済産業省は、2018年のDXレポートで「複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025 年までに予想されるIT人材の引退や、サポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は、2025年以降、最大12兆円/年(2018年現在の約3倍)にのぼる可能性がある」と指摘しました。この頃、国内では約8割にのぼる企業が老朽化やブラックボックス化などの問題を抱えるシステム(レガシーシステム)を利用しており、「DXが進まない」など課題を感じている企業は約7割あったことも言及されています。
7年の月日を経て2025年に突入した今、DXレポートで指摘されたレガシーシステムの問題を回避するには、実務で日々システムに触れている業務担当者も、他人事と考えず老朽化問題に意識を向けることが重要です。
企業が直面しやすいシステム老朽化のリスクと課題
老朽化したシステムを使い続けることは、目に見えないリスクの温床になるため、放置し続けると企業にとって様々な問題やリスクが発生しやすくなります。
ここでは、よく聞かれる「老朽化がもたらすリスク」を紹介します。
① セキュリティリスクの増大
自社サーバで運用するオンプレミス型システムの場合、ソフトウェアやハードウェアにはサポート期間が設けられています。しかし、サポート期間が終了すると、その製品に対するアップデートや問い合わせ等ができなくなります。当然、セキュリティも更新されなくなるため、そのまま放置しているとマルウェア感染や不正アクセスの標的にされやすくなります。
攻撃者は、企業のセキュリティの穴を狙って攻撃を仕掛けてきます。最新のセキュリティ対策が施されていないと、外部からの攻撃に対する耐性が低下し、データ漏洩やシステム破壊のリスクが高まる可能性があります。これらのリスクを低減するためには、定期的なセキュリティ監査や多要素認証の導入、脆弱性診断の実施など最新のセキュリティ対策が必要ですが、システムが老朽化していると、最新のセキュリティ機能を追加することが難しくなります。

② システム障害のリスク増大
システムが老朽化すると、ハードウェアの物理的劣化やソフトウェアの互換性問題によって障害が発生しやすくなります。例えば「メンテナンスが十分に行われていない」「長期間使用している」システムは、処理負荷の増加によりパフォーマンスが低下し、予期せぬクラッシュやデータの損失が発生するリスクが高まります。
特に、このような障害が基幹システムで発生すると、システム停止によって業務が滞り、関連部門にも大きな影響を及ぼしかねません。顧客対応の遅延や取引先とのトラブルにも発展しかねず、場合によっては取引停止や契約の見直しといった信頼性の低下につながるおそれもあります。

③ 属人化・ブラックボックス化が深刻になる
システムの設計や運用に関する情報が、特定の担当者の知識や経験に依存している場合、その担当者が退職するとシステムの維持が困難になります。古いシステムでは「当時担当していたベンダーが交代している」「開発当時の記録がない」なども起こりやすく、システム構造を把握できていないブラックボックス化も見られます。
システム内部の仕様やカスタマイズの内容が明確でないと、システムを刷新しようにも新しい技術や他のシステムとの統合が困難になり、企業のIT戦略全体に悪影響を及ぼします。その結果、業務の効率化やDX推進が妨げられるだけでなく、システムの更新や移行が不可能になるリスクも考えられます。
※ システムのブラックボックス化については、コラム「システムのブラックボックス化とは?対応策のカギは『標準化』と『つながる』ことにあり!」を参照ください。

④ 保守・運用コストの増加
オンプレミス型システムでは、スクラッチ開発をしているケースが多く見られます。この場合、法制度の改正などにあわせてシステム改修が必要になり、その都度、開発のための時間とコストが発生します。また、現在の業務プロセスに合わせて業務改善を行おうとすると、追加の開発費用が必要になり、保守費用も膨らみます。特に古いシステムでは、新しい技術との互換性にも問題が生じるため、ますますコストが膨らむ可能性が高くなります。

⑤ 業務効率の低下
構築当時の技術や仕組みのシステムは、最新技術に比べると処理速度が遅く、データ処理に時間がかかることで業務の停滞を招き、結果的に企業全体の生産性が低下する可能性があります。
また、従来の機能では進化した業務を処理できないため、新しい業務プロセスに対応できず手作業に戻ることもあります。手作業が増えると、従業員のストレスが高まり、ミスが発生しやすくなるリスクも懸念されます。

⑥ DX遅延による競争力低下
DX推進には、あらゆるデータを一元化し、様々なシステムやITツールで活用できる環境整備が必要になります。
古いシステムでは、他のシステムやITツールと連携できないことが多く、別途APIの開発などDXのためのシステム環境の再整備が必要になります。データに関しても、顧客データなど全社で扱うべき情報が部門ごとに管理されていることもよくあるため、DX化を進める前にどのデータが最新かつ全体を網羅しているのかを見極めなければなりません。
データを利活用できないことで社内DX推進が遅れると、意思決定のスピードにも影響を及ぼし、企業の競争力低下を招く恐れがあります。

システム老朽化の見極め方・7つのサイン
システムの老朽化は「見極めが困難」と思われがちですが、次のような状態になっている場合、老朽化が進んでいる可能性が高いと考えられます。
●システム老朽化の見極めサイン
- 一部の業務で手作業が発生している
- 操作性への不満が多くなっている
- エラーや障害の頻度が多い
- サポート終了予告を受けた
- 保守・運用費用が増加している
- 業務の属人化が発生している
- セキュリティが不安になってきた
1. 一部の業務で手作業が発生している
制度改正や事業拡大などの影響を受け、業務プロセスを見直すことがあります。しかし、様々な理由で改修を見送り、そのままシステムを使い続けていると、やがて実際の業務フローや運用ルールに即した対応ができなくなり、一部の業務で手作業や回避的な運用が常態化していきます。
手動での再入力やデータ加工時などに「本来であればシステム側で吸収できるのでは」と感じたら、老朽化の兆候と捉えてよいでしょう。
2. 操作性への不満が多くなっている
「処理速度が遅い」など、システムの操作性に不満を感じ始めると、業務効率に影響を及ぼします。また、新しい業務に対応できず手作業が発生している場合は、新しい機能の追加や改修が必要と言えます。
3. エラーや障害の頻度が多い
「ソフトを立ち上げられない」「ログインできない」など、頻繁なエラーメッセージや予期せぬシステムダウンが発生して業務が中断される場合、リプレイスの必要性が高まっている可能性が高いと考えられます。
4. サポート終了予告を受けた
ソフトウェアやハードウェアのサポート期間が終了すると、新機能の追加や修正プログラムの提供、システム品質の改善などが受けられなくなります。セキュリティリスクや互換性の問題が発生しやすくなるため、何らかのリプレイスが必要になります。
5. 保守・運用費用が増加している
ハードウェアやソフトウェアの修理・更新コストが年々増加している場合、リプレイスで改善する可能性があります。
6. 業務の属人化が発生している
システムの操作が特定の担当者しか分からなくなっている場合、属人化が発生している可能性があります。新しい担当者が操作を理解するのに時間がかかるか、引き継ぎが困難になっている場合は要注意です。
7. セキュリティが不安になってきた
サイバー攻撃が増加する昨今、現行システムのセキュリティ体制に不安を感じる企業は少なくありません。しかし、古いシステムでは最新のセキュリティ技術が追加できない可能性があります。どのようなセキュリティ対策が必要かを抽出し、現行システムに追加できるか見きわめが必要です。
システム老朽化問題の解決策|今とるべき選択肢はクラウド移行!
既存システムの延命はコストを抑える選択肢に見えますが、実際は、維持にかかる保守費用・個別開発・トラブル対応のコストが年々増加し、トータルコストが高くなるケースが多くなるため、得策とは言えません。システムの老朽化問題を解決するには、システムの刷新は必須でしょう。
システムを刷新するには、新しいオンプレミス(自社サーバ運用)に置き換える方法と、クラウドサービスを利用する方法があります。
●オンプレミスを選んだ場合の効果と弊害
オンプレミスを選択する場合、業務の停止を回避すべく既存システムの一部を改修しながら行うことになります。業務フローに大幅な変更が生じないため、従業員の負担を軽減できます。また、既存のデータを移動させずに最大限活用できるため、データ移行のリスクや手間を抑えられます。
しかし、いずれ「老朽化」の時期が再びやってくることは避けられません。そのたびに保守やアップデートが必要になり、コスト負担が増大します。
●クラウドサービスにした場合の効果と弊害
クラウドサービスなら、最新のIT技術を常に取り入れることができ、システム間のデータ連携もしやすいため、2025年問題の対策にもなります。特にソフトウェアまで丸ごと提供されるSaaS型クラウドサービスなら、導入が簡単かつ自社でアップデートする必要もなく、常に最新の技術・機能が利用できます。オンプレミスよりも初期投資が抑えられ、運用コストも平準化されるため、資金計画も立てやすくなります。
セキュリティ対策も自社で行う必要がなく、保守管理もベンダーに任せられるため、自社の管理負担が軽減され、長期的に安全な運用が期待できます。データ移行も通常業務と並行して行い、テスト運用を経てから完全移行となるため、移行時にトラブルが発生した場合でも業務への影響を最小限に抑えられます。
ただし、基本カスタマイズはできないため、クラウドサービスの仕様にあわせて業務プロセスを変更しなければならないことがあります。そのため、オンプレミス以上に自社の業務要件に適しているかの確認が重要になり、場合によっては業務プロセスをシステムにあわせることも視野に入れなければなりません。

そんなときは、奉行V ERPクラウドのように、業務に対応できる機能が網羅的に標準装備されているクラウドサービスを選べば、「業務要件にあわない」ケースを減らすことができます。それでも「完全」ではないため、標準機能をフル活用して対応できない業務には、業務特化型のクラウドサービスや、ノーコード・ローコード開発ツールと連携してカバーする方法も検討するのが、時流にあった対応策と言えるでしょう。

奉行V ERPクラウドの場合、100以上の業務系クラウドサービスとの連携が可能です。また、kintoneをはじめ多くのノーコード・ローコード開発ツールとも連携でき、カスタマイズしなくても自社の業務にあわせたシステム環境を整備できるようになっています。

このように機能性が高く業務のカバー力・応用力も備えたクラウドサービスを利用することで、できるだけ手間とコストをかけずに「システムの老朽化」問題を解決できます。
システム老朽化問題は早めにベンダーに相談を!
システムの老朽化は、企業にとって見過ごせないリスクです。現状では目に見えるトラブルがないからといって、老朽化したシステムを使い続けることほど企業経営において危険なことはありません。
ソフトウェアごと提供するSaaS型クラウドサービスなら、ITリソースの不足で悩む企業でも、安心してシステムを運用することが可能です。
“何も起きていない今”だからこそ、次の一手を打つ好機と考え、ベンダーに相談しながらシステムのクラウド化を進めませんか。
システムの老朽化でお悩みのご担当者さまへ
関連リンク
こちらの記事もおすすめ
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!