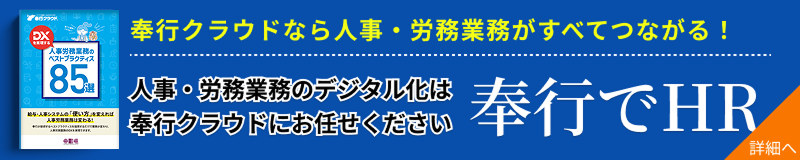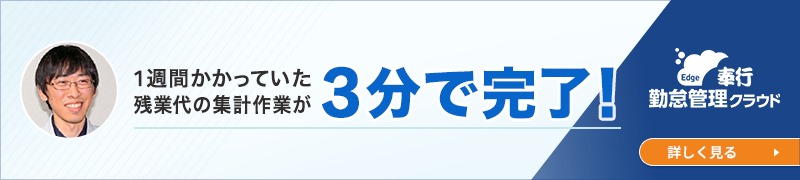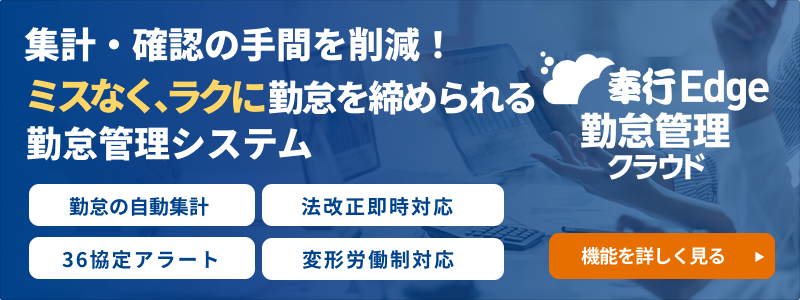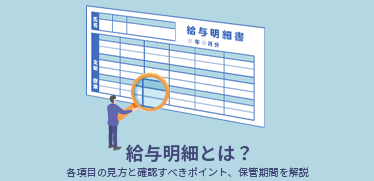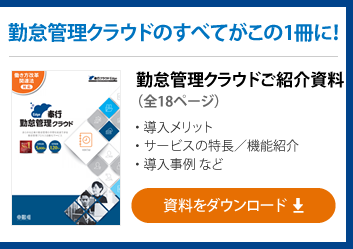働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、テレワークを導入する企業が増え、多様な働き方のひとつとして定着しつつあります。そこで課題となっているのが、テレワークにおける勤怠管理です。
本記事では、テレワークの勤怠管理における課題や、勤怠管理を行うための方法、注意点などを詳しく解説します。勤怠管理がテレワーク導入の課題になっている事業者や、テレワークの勤怠管理を見直したい事業者は、ぜひ参考にしてください。
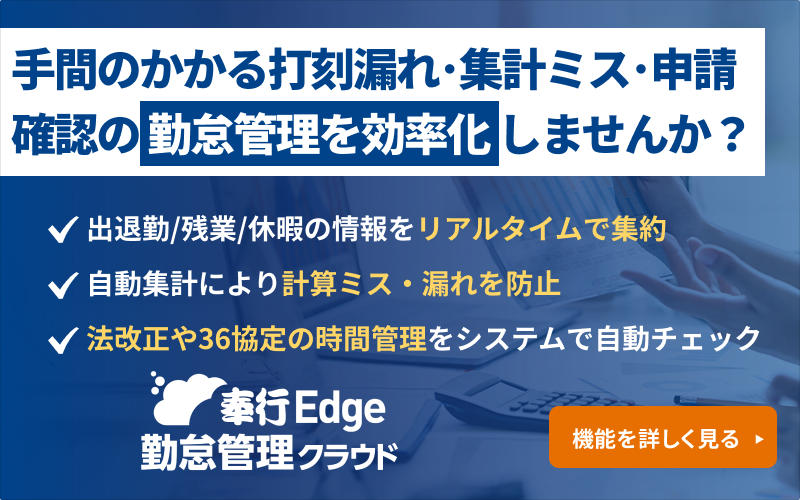
目次
- テレワークに関する勤怠管理の課題
- テレワークにおける勤怠管理の方法
- テレワークで始業・終業時刻を適切に管理するには?
- テレワークに役立つ勤怠管理システムとは?
- テレワークに役立つ勤怠管理システムの選び方
- テレワークにおける勤怠管理の注意点
- テレワークの勤怠管理の課題は、システム導入で解消できる
テレワークに関する勤怠管理の課題
テレワークを行う上で、勤怠管理に関するさまざまな課題が生じます。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の「令和2年度テレワークの労務管理に関する総合的実態調査研究事業報告書」によると、調査対象の3割以上の企業が「労働時間の申告が適正かどうかの確認が難しい」と、テレワークの課題を挙げています。
テレワークは、それぞれ自宅などで業務を行うことから、上司の目視による勤怠状況の確認ができません。いつ、どのように業務を行っているのかを目で見て確認できないため、上司の許可を得ていない中抜けやサービス残業、長時間労働などが生じるおそれがあります。
特に、タイムカードや生体認証、ICカードなど、事務所に来ないとタイムカードを打刻できないシステムを利用している企業では、労働時間をどのように管理するのか検討する必要があります。
※出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「令和2年度テレワークの労務管理に関する総合的実態調査研究事業報告書」
テレワークにおける勤怠管理の方法
テレワークにおける勤怠管理には、具体的にどのような方法があるのでしょうか。勤怠管理の方法の例を見ていきましょう。
メールやチャットなどによる報告
テレワークにおける勤怠管理のひとつに、メールやチャットなどのコミュニケーションツールで、始業と終業の時刻を上司に報告する方法があります。
メールやチャットがあれば手軽に導入できますが、「勤怠管理台帳への転記が必要」「メールやチャットに不具合があると正確な記録を残せない」「残業時間の計算が必要」などの難点があります。
臨時的なテレワークでの業務や、残業がほぼ発生しないなどの場合はおすすめの方法です。
電子ファイルの出勤簿などに自己申告で記入する
ExcelやWordなどの電子ファイルを出勤簿として共有フォルダに用意し、始業と終業の時刻を記入することでも勤怠管理は可能です。
こちらも手間やコストをかけずに手軽に導入しやすい方法ですが、完全自己申告になってしまうため、リアルタイムで報告が行われない、後から改ざんされてしまうなどの可能性があります。
また、複数の社員が同じファイルを利用する場合、誤って他者のデータに上書きしてしまうこともあるかもしれません。
ウェブ上で打刻する
勤怠管理システムを使用し、ウェブ上で打刻することで、テレワーク時でもリアルタイムに始業・終業を記録できます。
場所を問わずに勤怠登録ができるため、テレワークに適しています。また、打刻した時間がそのまま出退勤時間として登録されるので、虚偽の申告や打刻の間違えを心配する必要もありません。
こうした機能を利用するためには、専用のシステムを用意が必要です。クラウド上で利用できる勤怠管理システムを導入する場合が多く、従業員は専用アプリやウェブ上から出退勤を記録します。
勤怠管理システムにおける出退勤の記録は、「出勤・退勤ボタン」を押すだけなど、手間をかけずに行えます。また、「打刻時の位置情報を取得する」「打刻を忘れた際にアラートでお知らせする」などの機能を備えたシステムもあり、より正確な勤怠管理が可能です。
テレワークにおける正確な勤怠管理には、勤怠管理システムの導入がおすすめといえます。
テレワークで始業・終業時刻を適切に管理するには?
厚生労働省が示している勤怠管理に関するガイドラインでは、「労働時間の適正な把握のために使用者(事業側)が講ずべき措置」として、下記の2つを挙げています。
<始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法>
- (ア)使用者が、みずから現認することにより確認し、適正に記録すること
- (イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
※出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
(ア)は上司などが現認する必要があるため、テレワークでは困難です。テレワークでなくても上司が部下の誰よりも早く職場にいて、誰よりも遅く帰る状態でないと常に現認により確認できないため、現実的ではありません。
(イ)の客観的な記録にもとづく管理を行うためにも、テレワークにおける適切な勤怠管理には、勤怠管理システムの導入が必要といえます。
テレワークに役立つ勤怠管理システムとは?
勤怠管理システムとは、従業員が電子的に勤怠の入力を行い、自動集計できるシステムのことです。テレワークにおける打刻方法には、アプリ・ウェブ・チャットツールなど、さまざまな方法があります。
事務所にいなくても打刻できるシステムを利用することで、テレワークでも簡単に正確性の高い勤怠管理が可能になります。
勤怠管理システムの機能
勤怠管理システムの機能は、インターネットを介した打刻だけではありません。勤怠管理システムの主な機能は下記のとおりです。
<勤怠管理システムの主な機能>
- 労働時間や残業時間のリアルタイムでの自動集計
- 出退勤時刻とパソコンのログオフ時間の乖離の確認
- 各種申請と承認手続きのデジタル化
- シフト作成
- 帳票作成
- 残業時間管理
- 有給休暇管理
- 給与システムとの連携によるデータ取り込み
特にテレワークにおいては、出退勤時刻とパソコンのログオフ時間の乖離から、サービス残業の有無を確認できる機能が役立ちます。
「奉行Edge 勤怠管理クラウド 」のような勤怠管理システムなら、出退勤時刻とパソコンのログオフ時間の乖離を確認できます。労働状況を可視化できるため、労働時間の適正把握と長時間労働を防止できるでしょう。
また、各種申請と承認手続き、リアルタイムでの労働時間の自動集計機能などもテレワークで役立つ機能です。
長時間労働の防止や各種申請手続きが可能
残業時間が自動集計され、一定ラインを超えた際にアラートが出る機能を活用すれば、長時間労働を防げるでしょう。また、申請や承認手続きを勤怠管理システム上で行えば、各種申請手続きをインターネット上で完結できます。
勤怠管理システムは、労働時間の集計や給与システムとの連携も可能です。「給与奉行iクラウド 」のようなクラウドサービスの給与計算システムと連携するなど、労務担当者が自宅で作業できる環境が整っていれば、テレワークで給与計算もできます。
勤怠管理システムには、テレワークや業務効率化に役立つ多くの機能が搭載されています。ただし、システムの種類によって利用できる機能や、具体的な運用方法は異なるため、搭載している機能や使い勝手について確認しましょう。
テレワークに役立つ勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムには、さまざまな種類があります。ニーズに合わないシステムを導入してしまうと、「コストと手間をかけたわりに、希望の使い方ができなかった」といったことになりかねません。
テレワークの勤怠管理のためにシステムを導入する際には、下記のポイントに注意しましょう。
自社の勤務形態に沿った適切な勤怠管理ができるか
自社の勤務形態に応じた勤怠管理ができるかどうかは、システムを選ぶ際の大きなポイントです。
例えば、フレックスタイム制を導入している企業では、始業時間や終業時間が従業員の都合によって変動します。また、同じフレックスタイム制でも、コアタイムがあるかないかによって勤怠管理の方法が異なります。
さらに、社用パソコンやスマートフォンの有無、チャットツールを利用しているかどうかで、適した打刻方法も変わるため、自社に最適な勤怠管理システムかを確認しなければなりません。
コストが見合っているか
勤怠管理システムには、初期費用や年間利用料などのコストがかかります。導入時の費用と利用料が、自社にとって許容できる範囲に収まっているかどうかも検討材料のひとつです。
なお、手動で勤怠管理を行う場合、1つのミスでも修正に時間がかかります。勤怠管理システムの導入を検討する際は、システム化によるミスの低減なども考慮した上で、勤怠管理に費やす人件費との比較を行うとよいでしょう。
サポート体制が整っているか
導入時と運用時のサポート体制も、勤怠管理システムを選ぶにあたってチェックしておくべきポイントです。
導入時のサポートを受けられる勤怠管理システムなら、自社に最適な運用方法の提案や、操作方法の説明などを受けられます。システムに詳しくない担当者でも安心して導入できるのではないでしょうか。
また、運用中に不明点が生じた際や、トラブルが発生した際に受けられるサポート内容の確認も大切です。「メールサポートのみ」「電話」「画面共有を含めた通話」など、サポート方法についても事前に確認しておくと安心です。
そのほか、セキュリティ体制や法令改正へのアップデート対応、システムの安定性なども確認しておくことをおすすめします。
テレワークにおける勤怠管理の注意点
従業員にとっても企業にとってもテレワークがプラスになるよう、勤怠管理は適切に行う必要があります。テレワーク中の勤怠管理における注意点を確認しておきましょう。
ルールの徹底と周知
テレワークの勤怠管理では、ルールが徹底されていなかったり、従業員がルールを知らなかったりすることで、問題が起こりやすい傾向があります。そのため、「勤怠管理システムの使い方」「イレギュラーなことが発生したときの対処法」などをルール化し、従業員がいつでも確認できるようにしておかなければなりません。
例えば、「急用ができたので中抜けしたい」「昼休みの時間を変更したい」「早退したい」といったイレギュラーなことが生じた際の手続きについて、その都度、操作方法を調べる従業員もいます。
その際、どこを見れば良いのか、どのように手続きをすれば良いのかが明確であることが大切です。
また、「昼休みの時間変更は不可」といった企業独自の決まりがある場合は、その旨を明記しておかなければいけません。できることとできないことをはっきりさせておけば、従業員が迷うことなく適切な対応をとれるようになります。「書かれていない」という状況下では、独断で不適切な処理が行われることがあるため、注意が必要です。
サービス残業や過重労働を防ぐ対策
テレワークでは管理者が目視で勤怠状況を確認できません。サービス残業や過重労働を防ぐため、システム的に残業時間を管理できる体制づくりを行う必要があります。
具体的には、下記のような対策が考えられます。
・残業時間の上限に対するアラート機能がついた勤怠管理システムの導入
残業時間をリアルタイムで集計し、法令に定められた上限が近づいた際にアラートを出せる勤怠管理システムを導入する方法です。これにより、本人と管理者双方が残業時間を意識した働き方ができるようになります。
なお、残業時間は法令により、36協定を締結した場合で月45時間まで、特別条項付きの36協定を締結した場合で月100時間未満と定められています。ただし、特別条項付きの36協定を締結していても、2~6ヵ月の複数月の平均すべてが月80時間を超えることはできず、1年の上限は720時間以内です。これらを手動で集計するのは困難なため、自動的に判定してアラートが出せるシステムの利用がおすすめです。
・打刻とパソコンのログオフ時間を記録する勤怠管理システムの導入
「奉行Edge 勤怠管理クラウド」ような出勤退勤時刻と社用パソコンのログオフ時間を記録できる勤怠管理システムを導入することで、打刻時間と稼働時間が一致しているか確認ができます。
出退勤打刻とパソコンのログオフ時刻の乖離を可視化できれば、サービス残業の防止につながるでしょう。
・業務に必要なシステムへのログイン時間に制限をかける
一定の時刻を超えたタイミングで、業務に必要なシステムへのログインを求め、サービス残業や過重労働を防ぐ方法もあります。
「20時以降のログインには申請が必要」など時間を定め、残業の実態を把握できるようにします。
テレワークの勤怠管理の課題は、システム導入で解消できる
テレワークでは勤怠管理は大きな課題になり、特に正確性の高い労働時間の管理や長時間労働の防止は、テレワークの推進に必要不可欠といえます。
そこで役立つのが、勤怠管理システムです。出社しなくても出退勤時間を打刻できて、長時間労働に対するアラートなども可能なシステムを導入すれば、テレワークの勤怠管理をスムーズに行いやすくなります。
残業時間をリアルタイムで確認できる上、システム上で労働時間を確認したり、給与計算システムと連携をとったりすることもできるため、労務管理や給与計算業務のテレワークにもつながります。
OBCの「奉行Edge 勤怠管理クラウド 」なら、長時間労働者をひと目で確認できる帳票や、自動集計された勤務情報をもとにした「残業推移」「平均残業時間」など、さまざまな角度で勤怠状況を把握できます。
前述した、出退勤時刻とPCのログオフ時間の乖離を確認できる機能では、テレワークにおける労働時間の適正な把握や、長時間労働の防止に役立ちます。
また、「給与奉行iクラウド」はもちろん、それ以外の給与計算ソフトともCSV連携が可能です。
アプリ上からの打刻やアラート、シフト作成、申請・承認など、あらゆる勤怠管理関連業務を一括してデジタル化できますので、テレワークの勤怠管理にお役立てください。
 ■ 給与奉行iクラウド デモンストレーション
■ 給与奉行iクラウド デモンストレーション

■監修者
山本 喜一
特定社会保険労務士、精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に技術職として勤務し、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。
関連リンク
こちらの記事もおすすめ
OBC 360のメルマガ登録はこちらから!